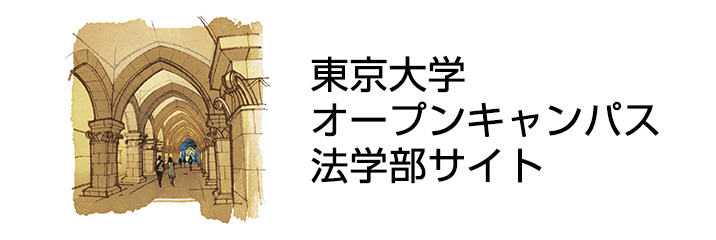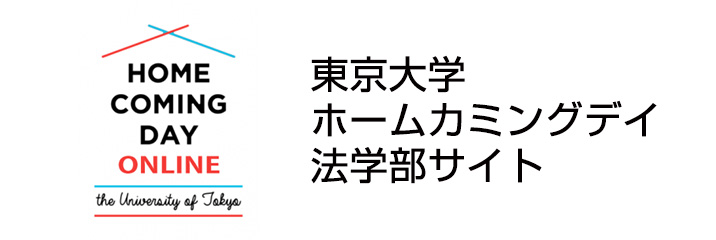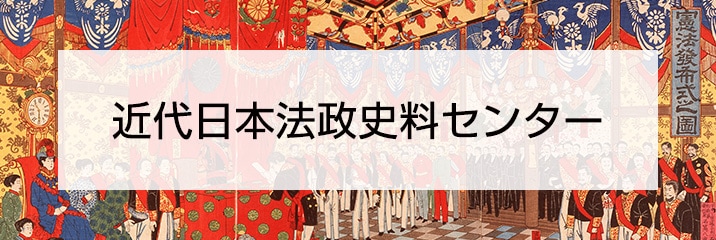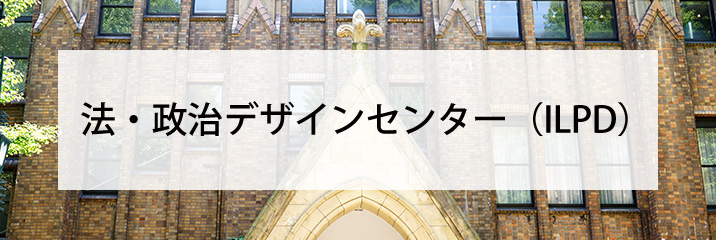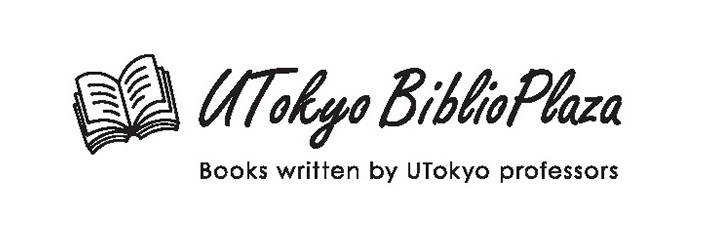加毛 明(かも あきら)
教授
研究分野:民法
KAMO AkiraProfessor
Areas of Interest: Civil Law
略歴
2003年3月 東京大学法学部卒業(学士(法学))
2003年4月 東京大学大学院法学政治学研究科助手
2006年4月 東京大学21世紀COEプログラム特任研究員
2006年7月 東京大学大学院法学政治学研究科助教授
2007年4月 東京大学大学院法学政治学研究科准教授
2019年7月 東京大学大学院法学政治学研究科教授
2009年9月~2010年6月 イェール・ロー・スクール 客員研究員
2010年9月~2011年7月 ミュンヘン大学 比較法研究所 客員研究員
2020年10月~2021年8月 フランクフルト大学 国際私法・ヨーロッパ私法及び比較法研究所 客員研究員
2022年1月~ 東京大学社会科学研究所 研究担当
2023年12月~ 金融庁金融研究センター 特別研究員
2024年10月~ 日本銀行金融研究所 国内研究員
関心分野
民法、信託法、比較法
担当授業科目
【学部】民法第1部~第4部、消費者法、民法基礎演習、民法演習
【大学院】基本科目民法1~3、上級民法1・2、信託法、消費者法、民事系判例研究、民法演習、信託法演習
所属学会
日本私法学会、信託法学会、金融法学会
近年の学内・研究科内の主要な役職
図書・学術情報委員会委員(2007年4月~2009年3月、2014年4月~2020年3月)
入学時期等検討ワ-キンググループ(2012年6月~2013年6月)
緑会評議員(2016年4月~2018年3月)
公的活動等
【公官庁】
法務省・法制審議会・民法(成年後見等関係)部会・臨時委員(2024年4月~)
内閣府・消費者委員会・消費者制度のパラダイムシフトに関する専門調査会・専門委員(2023年12月~)
法務省・法制審議会・区分所有法制部会・幹事(2022年10月~2024年3月)
経済産業省・産業構造審議会・臨時委員(2018年7月~2020年7月)
割賦販売小委員会・委員(2019年2月~2019年12月)
Connected Industriesにおける共通商取引ルール検討小委員会・委員(2018年7月~2018年12月)
最高裁判所・裁判所書記官等試験委員会・臨時委員(2015年11月~2017年8月)
金融庁・金融審議会・専門委員(2014年10月~2020年10月)
金融制度スタディ・グループ・メンバー(2017年11月~2019年7月)
金融制度ワーキング・グループ・委員(2016年7月~2016年12月)
決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ・委員(2015年7月~2015年12月)
決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ・委員(2014年10月~2015年4月)
法務省・民事局・調査員(2006年7月~2009年6月)
【民間団体】
公益社団法人商事法務研究会(消費者庁委託事業)・消費者被害の拡大を防止するための実効性の高い手法等に関する研究会・委員(2024年6月~)
株式会社野村総合研究所(経済産業省委託事業)・GX 実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会・委員(2024年5月~)
リーテックス株式会社・デジタル証明研究会・メンバー(2024年4月~)
みずほ情報総研株式会社(経済産業省委託事業)・Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会・委員(2020年8月~2020年9月)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所(経済産業省委託事業)・新たなガバナンスモデル検討会・委員(2019年8月~2020年3月)
東京大学生活協同組合・理事(2019年5月~2020年5月)
日本IT団体連盟
情報銀行推進委員会・認定委員会・委員(2018年11月~2020年10月)
情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会・構成員(2017年11月~2018年3月、2019年1月~2019年3月、2019年4月~2020年3月)
【学会】
日本私法学会
幹事(2006年7月~2009年6月、2011年7月~2015年10月)
運営懇談会委員(2006年10月~2014年10月)
信託法学会
幹事(2022年6月~)
主要著作
【著書】
『契約法の基層と革新』(東京大学出版会・2024年)〔共編著〕〔はしがき、第8章〕
『条解信託法』(弘文堂・2017年)〔共著〕〔23条~25条、216条~247条〕
『解説 民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣・2017年)〔共著〕〔第2章 改正法の内容;第5節 債務不履行等、第12節 債権の譲渡等、第13節 弁済等、第14節 相殺等〕
【論文】
「外国法の比較研究における共通性と差異」石川博康=加毛明編『契約法の基層と革新』(東京大学出版会・2024年)211-246頁
「情報の取引と信託」神作裕之=三菱UFJ信託銀行フィデュ-シャリー・デューティー研究会編『フィデューシャリー・デューティーの最前線』(有斐閣・2023年)1-46頁
「決済手段の移転に関する私法上の法律問題――資金移動業電子マネーを中心として」沖野眞已ほか編『これからの民法・消費者法(Ⅰ)(河上正二先生古稀記念)』(信山社・2023年)245-271頁
「金銭その他の支払手段の預かりに関する規制について」金融法研究39号(2023年)59-76頁
「金融機関と顧客の仲介に関する法的課題(上)(中)(下)」法律時報94巻12号(2022年)85-93頁、95巻1号(2023年)119-126頁、95巻2号(2023年)62-69頁
「信託法研究の変遷と展望」信託法研究46号(2022年)3-31頁
「信託法・信託業法の百年――私法学の観点から」信託290号(2022年)5-16頁
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策目的での普通預金規定の改定をめぐる私法上の諸問題」金融法務研究会『社会的要請の変化を踏まえた銀行取引における現代的課題』(全国銀行協会・2022年)〔第6章〕1-18頁
「アメリカ法における被相続人のデジタル情報に対する人格代表者のアクセス──Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Actを巡る議論を素材として」岡本裕樹ほか編『民法学の継承と展開(中田裕康先生古稀記念)』(有斐閣・2021年)921-967頁
「民法(相続関係)改正と遺言による貸金庫内容物の承継」金融法務研究会『民法(相続関係)改正に伴う銀行実務への影響』(全国銀行協会・2021年)〔第4章〕1-29頁
「デジタル・トークンと法」堀天子編『暗号資産の法的性質と実務〔金融・商事判例1611号〕』(経済法令研究会・2021年)6-12頁
「第239条~第241条(無主物の帰属・遺失物拾得・埋蔵物発見)」吉田克己編著『物権法の現代的課題と改正提案』(成文堂・2021年)498-536頁
「ミズーリ州における相続財産の承継手続――遺産管理手続を中心として」道垣内弘人編『各国における遺言執行の理論と実態』(トラスト未来フォーラム・2020年)179-226頁
「海外金融法の動向(イングランド) イギリスにおけるRegTech実現への取組み――規制上の報告のデジタル化(Digital Regulatory Reporting)プロジェクト」金融法研究36号(2020年)114-130頁
「民法(相続関係)改正と遺言による普通預金の承継」金融法務研究会『最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)を踏まえた預金債権の相続に関する諸論点』(全国銀行協会・2020年)67-101頁
「法人における事実認識の有無に関する法的判断の構造」神作裕之編『フィデューシャリー・デューティーと利益相反』(岩波書店・2019年)171-227頁
「仮想通貨の私法上の法的性質――ビットコインのプログラム・コードとその法的評価」金融法務研究会『仮想通貨に関する私法上・監督法上の諸問題の検討』(全国銀行協会・2019年)1-34頁
「新しい契約解除法制と倒産手続――倒産手続開始後における契約相手方の法定解除権取得の可否」事業再生研究機構編『新しい契約解除法制と倒産・再生手続』(商事法務・2019年)182-241頁
「新しい契約解除法制総論――催告解除、無催告解除、約定解除」事業再生研究機構編『新しい契約解除法制と倒産・再生手続』(商事法務・2019年)16-37頁
「信託社債と倒産手続」河上正二=大澤 彩編『人間の尊厳と法の役割――民法・消費者法を超えて(廣瀬久和先生古稀記念)』(信山社・2018年)143-164頁
「受益権の譲渡性・差押可能性の制限――浪費者信託との比較において」樋口範雄=神作裕之編『現代の信託法――アメリカと日本』(弘文堂・2018年)47-99頁
「海外金融法の動向(イングランド) イギリスにおけるフィンテック関連政策の展望」金融法研究34号(2018年)127-147頁
「民法(債権関係)改正と債権譲渡――譲渡制限の意思表示に関する民法改正が金融実務に与える影響」金融法務研究会『民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題』(全国銀行協会・2018年)15-42頁
「限定責任信託と不法行為責任」能見善久ほか編『信託法制の新時代――信託の現代的展開と将来展望』(弘文堂・2017年)127-144頁
「遺言執行――民法の規定の特色とその背景」法律時報89巻11号(2017年)46-53頁
「海外金融法の動向(イングランド) オープン・バンキング・フレームワークの導入をめぐる法的諸問題」金融法研究33号(2017年)131-145頁
「欧米におけるインターネット・バンキングの無権限取引に関する金融機関の責任範囲」金融法務研究会『金融商品・サービスの提供、IT技術の進展等による金融機関の責任範囲を巡る諸問題』(全国銀行協会・2017年)40-86頁
「19世紀アメリカにおける大学附属ロー・スクール――イェール・ロー・スクールを中心として」東京大学法科大学院ローレビュー11号(2016年)236-267頁
「海外金融法の動向(イングランド)デジタル通貨(仮想通貨)をめぐる議論状況」金融法研究32号(2016年)128-138頁
「預金債権を『相続させる』旨の遺言と遺言執行者の職務権限」金融法務研究会『銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題』(全国銀行協会・2016年)61-78頁
「共和政初期アメリカにおける法学教育――リッチフィールド・ロー・スクールを中心として」東京大学法科大学院ローレビュー10号(2015年)80-102頁
「信託と破産(1)~(3・完)――信託財産の破産と受託者の破産に関する解釈論上の諸問題」NBL1053号(2015年)4-15頁、1054号(2015年)45-51頁、1055号43-49頁(2015年)
「ドイツにおける顧客財産保護にかかる法制度――有価証券寄託法を中心として」金融研究34巻3号(2015年)67-99頁
“Blick aus Japan auf die deutsche Schuldrechtsmodernisierung – Ein Studium über die Rechtsübertragung”, Markus Artz, Beate Gsell u. Stephan Lorenz (Hrg.), Zehn Jahre Schuldrechtsmodernisierung (Mohr Siebeck, 2014) SS. 121-136; Zeitschrift für Japanisches Recht, Nr. 38, SS. 171-187 (2015).
「信託の現代的展開――受託者の破産手続における信託債権の取扱いについて」吉田克己=片山直也編『財の多様化と民法学』(商事法務・2014年)586-597頁
「主観的事情と認識帰属の法理」樋口範雄=佐久間毅編『現代の代理法――アメリカと日本』(弘文堂・2014年)138-174頁
“Crystallization, Unification, or Differentiation? The Japanese Civil Code (Law of Obligations) Reform Commission and Basic Reform Policy”, Columbia Journal of Asian Law, vol. 24, pp. 171-212 (2012).
「信託元本・収益の調整とユニトラストへの転換」樋口範雄編『外から見た信託法』(トラスト60・2010年)97-114頁
「受託者破産時における信託財産の処遇」私法70号(2008年)124-130頁
「受託者破産時における信託財産の処遇(1)~(4・未完) ――二つの『信託』概念の交錯」法協124巻2号(2007年)394-489頁、11号2387-2439頁(2007年)、125巻1号(2008年)65-134頁、12号2645-2690頁(2008年)
【判例評釈・判例解説・書評など】
「時効消滅した債権による相殺と相殺適状の要件」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ[第9版]』(有斐閣・2023年)64-65頁
「預金債権の帰属」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ[第9版]』(有斐閣・2023年)130-131頁
「時効消滅した債権による相殺と相殺適状の要件」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ[第8版]』(有斐閣・2018年)78-79頁
「預金債権の帰属」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ[第8版]』(有斐閣・2018年)148-149頁
「民法のための弁明――民法学者の仕事」書斎の窓644号(2016年)26-31頁〔書評:大村敦志=小粥太郎著『民法学を語る』(有斐閣・2015年)〕
「「相続させる」旨の遺言と登記」水野紀子ほか編『民法判例百選Ⅲ』(有斐閣・2015年)150-151頁
「相殺適状の要件」中田裕康ほか編『民法判例百選Ⅱ[第7版]』(有斐閣・2015年)88-89頁
「預金債権の帰属」中田裕康ほか編『民法判例百選Ⅱ[第7版]』(有斐閣・2015年)148-149頁
「所有権留保と民事再生手続」伊藤眞ほか編『倒産判例百選』(有斐閣・2013年)118-119頁
「信託の変更・終了」樋口範雄ほか編『アメリカ法判例百選』(有斐閣・2012年)220-221頁
「預金債権の帰属」中田裕康ほか編『民法判例百選Ⅱ[第6版]』(有斐閣・2009年)144-145頁
「相続させる旨の遺言と登記」水野紀子ほか編『家族法判例百選[第7版]』(有斐閣・2008年)156-157頁
「民法と他領域⑹信託法」内田貴=大村敦志編『新・法律学の争点シリーズ 民法の争点』(有斐閣・2007年)18-19頁
「最高裁判所民事判例研究(民集五七巻二号)損害保険料保管専用口座に関する預金者の認定(最高裁二小法廷平成15年2月21日)」法協121巻11号(2004年)1961-1997頁
【パネルディスカッション・座談会など】
「パネルディスカッション デジタル・アーキテクチャと法に関するシンポジウムーーデジタル・アーキテクチャの社会実装・運用に係る諸問題」NBL1246号(2023年)8-27頁〔加毛明、宍戸 常寿、〕
「パネルディスカッション シンポジウム 信託法制定100年」信託法研究46号(2022年)67-92頁〔加毛明、神田秀樹、木南敦、後藤元、佐久間毅、溜箭将之、道垣内弘人、能見善久、樋口範雄〕
「決済法制および金融サービス仲介法制に関する論点と展望――〔第3部〕金融サービス仲介」金法2139号(2020年)42-64頁〔加藤貴仁、加毛明、坂勇一郎、堀天子、丸山弘毅、森下哲朗、伊藤誠治、木村康宏、瀧 俊雄〕
「決済法制および金融サービス仲介法制に関する論点と展望――〔第2部〕前払式支払手段・収納代行」金法2138号(2020年)50-72頁〔加藤貴仁、加毛明、坂勇一郎、堀天子、丸山弘毅、森下哲朗、石井真弘、片岡康子、木村 健太郎、田中 芳樹〕
「決済法制および金融サービス仲介法制に関する論点と展望――〔第1部〕資金移動業関係」金法2137号(2020年)10-37頁〔加藤貴仁、加毛明、坂勇一郎、堀天子、丸山弘毅、森下哲朗、池田憲彦、磯和啓雄、越智一真〕
「金融法制の現代的課題(上)(下)――情報、決済、プラットフォーマーをめぐって」金法2109号(2019年)6-23頁、2110号(2019年)70-91頁〔大澤正和・落合孝文・加藤貴仁・加毛明・坂勇一郎・瀧俊雄・丸山弘毅・森下哲朗〕