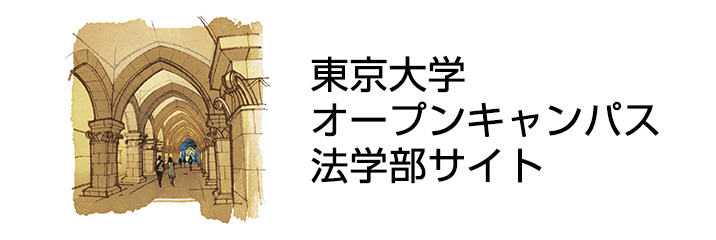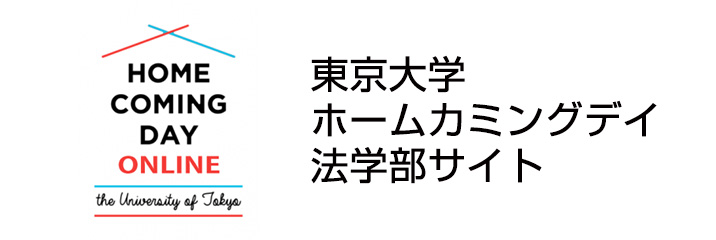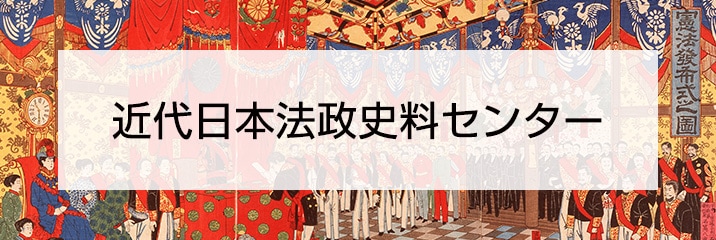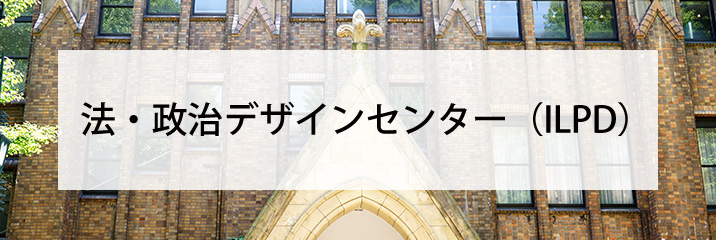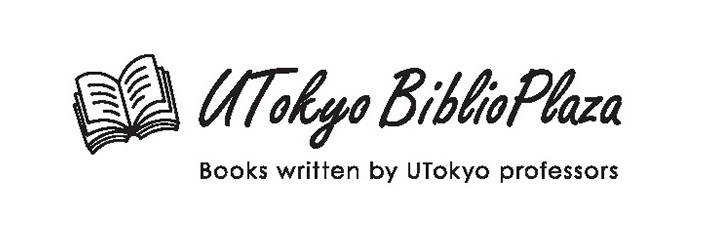小島 慎司(こじま しんじ)
教授
研究分野:憲法
KOJIMA ShinjiProfessor
Areas of Interest: Constitutional Law
略歴
2001年 東京大学法学部卒業
2003年 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了
2006年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学(博士(法学))
2007年 上智大学法学部講師
2009年 上智大学法学部准教授
2016年 東京大学大学院法学政治学研究科准教授
2018年 東京大学大学院法学政治学研究科教授
関心分野
憲法
担当授業科目
憲法関連科目
所属学会
日本公法学会、全国憲法研究会、日仏法学会
主要著作
Ⅰ 著作
・『制度と自由 モーリス・オーリウによる修道会教育規制法律批判をめぐって』(岩波書店、2013年3月)
Ⅱ 論文
・「主権を欠いた政治体について オリヴィエ・ボーの連邦論を読む」国家学会雑誌116巻11=12号(有斐閣、2003年)156-207頁
・「近代国家の確立と制度体の自由(1)~(5完)モーリス・オーリウ『公法原理』第二版における修道会教育規制法律への批判の分析」国家学会雑誌121巻3=4号(有斐閣、2008年4月)293-354頁、121巻5=6号(2008年6月)537-586頁、121巻7=8号(2008年8月)699-748頁、121巻9=10号(2008年10月)831-889頁、121巻11=12号(2008年12月)1144-1212頁
・「『名誉』の放棄」上智法学論集52巻1=2号(上智大學法學會、2008年12月)1-24頁
・「『教育の自由』」安西文雄ほか著『憲法学の現代的論点〔第2版〕』(有斐閣、2009年9月)421-438頁
・「取引と法人格」ジュリスト1378号(有斐閣、2009年5月)55-61頁
・「国民主権の原理 (特集 憲法–統治機構論入門)」法学セミナー54巻11号(日本評論社、2009年11月)24-27頁
・「公法における『目的』」上智法学論集54巻2号(上智大學法學會、2010年12月)53-86頁
・「制度と人権」長谷部恭男編『講座人権論の再定位3 人権の射程』(法律文化社、2010年11月)48-63頁
・「比例原則 フランスの場合」上智法学論集56巻2=3号(上智大學法學會、2012年12月)71-79頁
・「判例における『制度的思考』」法学教室388号(有斐閣、2013年1月)13-22頁
・「選挙権権利説の意義 プープル主権論の迫力」論究ジュリスト5号(有斐閣、2013年5月)49-56頁
・「国民主権の原理」南野森編『憲法学の世界』(日本評論社、2013年7月)38-48頁
・「『経済的自由』」南野森編『憲法学の世界』(日本評論社、2013年7月)232-44頁
・「所有権の保障と立法者の消極的無権限」フランス憲法判例研究会編『フランスの憲法判例Ⅱ』(信山社、2013年3月)356-359頁
・「代表説の挑戦」長谷部恭男ほか編『高橋和之先生古稀記念 現代立憲主義の諸相 上』 (有斐閣、2013年12月)37-62頁
・「日本における制度法学の受容」岡田信弘, 笹田栄司, 長谷部恭男編『高見勝利先生古稀記念論集 憲法の基底と憲法論 : 思想・制度・運用』(信山社、2015年5月)259-282頁
・「命令委任とその否定の意味 私法上の委任との関係を踏まえて」日仏法学28号21-42頁(日仏法学会、2015年7月)
・「近代社会における1つの友誼 プープル主権論について」憲法問題26号(三省堂、2015年5月)95-108頁
・「平和と秘密 永遠平和のための秘密条項について」 法律時報87巻10号(日本評論社、2015年9月)80-85頁→ 若干加筆後以下に所収・「平和と秘密 永遠平和のための秘密条項について」辻村みよ子ほか編『「国家と法」の主要問題』(日本評論社、2018年3月)121-133頁
・「苫米地事件」論究ジュリスト17号34-40頁(有斐閣、2016年4月)→ 若干加筆後以下に所収・「苫米地事件」長谷部恭男編『論究憲法 憲法の過去から未来へ』(有斐閣、2017年5月)65-77頁
・「憲法上の自由に対する事実上の制約について」上智法学論集59巻4号(上智大學法學會、2016年3月)75-93頁
・「オーリウの制度理論」論究ジュリスト18号(有斐閣、2016年8月)150-173頁(報告・座談会に参加)
・「主権論の展望と課題 主権・執政・自由」辻村みよ子編集代表『政治変動と立憲主義の展開』(信山社、2017年3月)83-93頁
・「非常事態の法理」論究ジュリスト21号(有斐閣、2017年4月)13-20頁
・「技術の精神 日本におけるフランスの法人論の受容について」北大法学論集68巻3号(北海道大学大学院法学研究科、2017年9月)53-70頁
・「制度と公開・均衡(1)~(4完) モーリス・オーリウによる大統領選出方法改革の提唱をめぐって」国家学会雑誌130巻7=8号(有斐閣、2017年8月)519-553頁、130巻9=10号(2017年10月)677-723頁、130巻11=12号(2017年12月)855-891頁、131巻1=2号 (2018年2月)57-94頁
・「国民主権」宍戸常寿、林知更編『総点検 日本国憲法の70年』(岩波書店、2018年3月)40-49頁
・「ポスト産業社会の労働における自由と従属 アラン・シュピオ『数字によるガバナンス』を手がかりにして(上)(下)」情報法制研究4号(有斐閣、2018年11月)36-45頁、5号(有斐閣、2019年5月)44-54頁
・「憲法上の権利の防御権的構成について」上智法学論集62巻3=4号(上智大學法學會、2019年3月)253-263頁
・「堀越判決と国家公務員の政治的行為に対する制裁の問題」論究ジュリスト29号(有斐閣、2019年5月)43-50頁
・「民主政下の専門職能」論究ジュリスト33号(2020年)15-22頁
・「丸山真男「「である」ことと「する」こと」と憲法学」国家学会雑誌133巻3=4号 259-276頁(2020年)
・« L’autonomie et l’allégeance des salariés. A propos de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot », Actes du XIIe SÉMINAIRE FRANCO JAPONAIS DE DROIT PUBLIC (Université d’Hiroshima, 15-17 mars 2018), Société de Législation Comparée, 2020, pp. 157-64
https://legiscompare.fr/ecommerce/fr/e-slc-collection-electronique/814-xiie-seminaire-franco-japonais-de-droit-public.html
・「憲法における比例原則」『第10回日仏共同研究集会報告集 利益の衡量』(ICCLP Publications No. 15,2020年)77-81頁,« Le principe de proportionnalité en droit constitutionnel », *Balance des intérêts. Xe rencontres juridiques franco-japonaises*, Société de législation comparée, 2025, pp. 91-97
・「違憲審査の手法(違憲審査基準・比例原則)」横大道聡ほか編『グローバル化のなかで考える憲法』(弘文堂,2021年)349-60頁
・「紀律法の誕生」上智法学論集65巻4号(上智大學法學會,2022年)281-99頁
・「議院内閣制」只野雅人編集『講座立憲主義と憲法学(4)統治機構』(信山社,2023年)247-267頁
・「フランスの人格権論の動向に関するノート」青井未帆ほか編『現代憲法学の理論と課題 野坂泰司先生古稀記念』(信山社,2023年)155-173頁
・「人権と公共の福祉」法律時報95巻11号(2023年)119-124頁
・« Maurice Hauriou et la métaphysique : à propos de sa critique contre la « philosophie nouvelle » dans le monde du droit », in Voyages et rencontres en droit public. Mélanges en l’honneur de Ken Hasegawa (Mare & Martin, 2023), pp. 379-391
・「衛生危機におけるリスク管理——日本法からの視点——」磯部哲ほか『公衆衛生と人権 フランスと日本の経験を踏まえた法的検討』(尚学社、2024年)35-41頁 ; « La gouvernance des risques au Japon : un déficit d’impérativité ? », in Guillaume Rousset, Philippe Pédrot, Tetsu Isobe et Haluna Kawashima, Concilier santé et droits fondamentaux en période de pandémie – Une analyse juridique des expérience (Bruylant, avril 2024), pp. 49-56
・「政教分離と信教の自由(上・下)」法律時報96巻8号83-89頁(2024年),9号91-97頁
・「準死についてーー人に関する研究ノート」増井良啓ほか編『市場・国家と法 中里実先生古稀祝賀論文集』(有斐閣、2024年8月)469-85頁
・「国民主権と代表制」高橋和之=長谷部恭男編『芦部憲法学——軌跡と今日的課題』(岩波書店,2024年9月)453-73頁
・« La responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles au Japon et en France » (en collaboration avec Cécile Guerin-Bargues), *Revue internationale de droit comparé*, 2025, n°1, pp. 9-23.
・「シャルル・アイゼンマンの国家作用論」斎藤誠=山本隆司編『行政法の理論と実務 宇賀克也先生古稀記念』(有斐閣,2025年8月)75-90頁
Ⅲ 教科書・註釈書・教材など
・憲法判例研究会編『判例プラクティス憲法』(信山社、2012年3月)「思想・良心の自由」(51-59事件)、「信教の自由」(60-65事件)、「政教分離」(66-74事件)、「学問の自由と教育を受ける権利」(136-148事件)、「適正手続」(173-179事件)、「社会権(2)労働基本権」(230-240事件)を担当
・憲法判例研究会編『判例プラクティス憲法 [増補版]』(信山社、2014年6月)「思想・良心の自由」(51-59事件)、「信教の自由」(60-65事件)、「政教分離」(66-74事件)、「学問の自由と教育を受ける権利」(136-148事件)、「適正手続」(173-179事件)、「社会権(2)労働基本権」(230-240事件)を担当
・憲法判例研究会編『判例プラクティス憲法 [第3版]』(信山社、2022年11月)「思想・良心の自由」(61-70事件)、「信教の自由」(71-76事件)、「政教分離」(77-88事件)、「学問の自由と教育を受ける権利」(170-183事件)、「適正手続」(214-220事件)、「社会権(2)労働基本権」(275-286事件)を担当
・木下昌彦編集代表『精読憲法判例[人権編]』(「法の下の平等(1)」(4-6事件)を担当)(弘文堂、2018年2月)
・木下昌彦編集代表『精読憲法判例[統治編]』(「裁判所(1)」(20-23事件)を担当)(弘文堂、2021年5月)
・重要事件タイムライン「衆議院の解散」(有斐閣オンライン、2024年6月)https://yuhikaku.com/articles/-/19527
・『憲法』(新世社,2025年10月)
・重要事件タイムライン「靖国神社公式参拝」(有斐閣オンライン,2025年12月)https://yuhikaku.com/articles/-/57597
IV 判例評釈
・「行政判例研究」自治研究78巻5号(第一法規、2002年5月)110-123頁
・「最高裁判所民事判例研究」法学協会雑誌122巻3号(有斐閣、2005年)122-149頁
・「インターネットの出現は名誉毀損罪の判例法理を変えうるか」Journalism242号(朝日新聞社ジャーナリスト学校、2010年7月)48-54頁
・「内申書の記載内容と生徒の思想・信条の自由」『憲法判例百選Ⅰ〔第6版〕』(有斐閣、2013年11月)79-80頁
・「成年被後見人は選挙権を有しないとする公選法11条1項1号の合憲性」判例セレクト2013(I)(法学教室401号別冊付録)(有斐閣、2014年1月)11頁
・「警察によるイスラム教徒の個人情報の収集・保管・利用の合憲性」ジュリスト臨時増刊1479号 平成26年度重要判例解説(有斐閣、2015年4月)16-17頁
・「郵便法による責任制限の合憲性」宇賀克也ほか編『行政判例百選[第7版]』(有斐閣、2017年11月)502-503頁
・「死者の名誉毀損 『落日燃ゆ』事件」長谷部恭男ほか編『メディア判例百選[第2版]』(有斐閣、2018年12月)78-79頁
・「内申書の記載内容と生徒の思想・信条の自由」『憲法判例百選Ⅰ〔第7版〕』(有斐閣、2019年11月)76-77頁
・「争議権の限界――生産管理・山田鋼業事件」『憲法判例百選Ⅱ〔第7版〕』(有斐閣、2019年11月)348頁
・「通達課税と租税法律主義」『憲法判例百選Ⅱ〔第7版〕』(有斐閣、2019年11月)383頁
・「内申書の記載内容と生徒の思想・信条の自由」『憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕』(有斐閣、2025年9月)74-75頁
・「争議権の限界――生産管理・山田鋼業事件」『憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕』(有斐閣、2025年9月)323頁
・「参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性」『憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕』(有斐閣、2025年9月)334-35頁
・「通達課税と租税法律主義」『憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕』(有斐閣、2025年9月)355頁
V その他(書評・座談会・寄稿等)
・「学界展望」国家学会雑誌118巻5=6号(有斐閣、2005年6月)272-276頁
・「学界展望」国家学会雑誌121巻3=4号(有斐閣、2008年4月)242-247頁
・書評「粕谷友介『自由・平等への異議申立人は』」ソフィア56巻4号(創文社、2008年6月)588-91頁
・「日本国憲法研究⑦思想・良心の自由」[コメンテーター]ジュリスト1395号(2010年3月)122-136頁
・「モーリス・オーリウに見る法学者の在り方」青淵777号(渋沢青淵記念財団竜門社、2013年12月)20-22頁
・「戦後憲法学の70年を語る:高橋・高見憲法学との対話(第1回~第12回)」[座談会に参加]法律時報89巻9号(日本評論社、2017年)~90巻8号(2018年)→解題を付して、宍戸常寿ほか編『戦後憲法学の70年を語る 高橋和之・高見勝利憲法学との対話』(日本評論社,2020年)
・翻訳「法と宗教(間規範性)」レジーヌ・アズリア=ダニエル・エルヴュー・レジェ編『宗教事象辞典』(みすず書房,2019年)671-685頁
・書評「春山習著『フランス第三共和制憲法学の誕生』等」 法制史研究68号(成文堂、2019年)365-368頁
・「法学教育のこれからと,これからの『法学教室』」[座談会に参加]法学教室 481号(2020年)4-20頁
・「古典の具体例をたどる」森田果『法学を学ぶのはなぜ?』(有斐閣,2020年)142-43頁
・「『人権の感覚』」法学教室482号(2020年)1頁
・「憲法学への誘い」法学セミナー795号(2021年)12-19頁
・「憲法の学び始めと条文―憲法21条を例に」法学教室488号(2021年)10-13頁
・「人民主権」法学教室489号(2021年)1頁
・「全国民の代表」法学教室496号(2022年)1頁
・「人についての2層の議論――本特集へのご案内」法学教室498号(2022年)10-13頁
・「フランス人権宣言第16条」法学教室503号(2022年)1頁
・「『主権の諸部分』の理論」法学教室510号(2023年)1頁
・書評「上村剛著『権力分立論の誕生――ブリテン帝国の『法の精神』受容』(岩波書店,2020年)」法制史研究72号(2023年)484-90頁
・「人に関わる4つの論文」飯田高ほか編『リーガル・ラディカリズム――法の限界を根源から問う』(有斐閣,2023年)344-48頁
・「警職法改正問題」法学教室517号(2023年)1頁
・「新二重基準論」法学教室524号(2024年)1頁
・「国民衛兵」法学教室531号(2024年12月)1頁
・ 翻訳(共訳) リチャード・タック『眠れる主権者』(勁草書房,2025年3月)
・「主権と統治」法学教室538号(2025年7月)1頁
・「土井翼『名宛人なき行政行為の法的構造』をめぐって(1-3)」有斐閣オンライン(2025年8月,座談会に参加)
・「令状なしで『逮捕』?」東京大学法学部「現代と法」委員会編『さらに、法学を知りたい君へ』(有斐閣、2025年9月)1-16頁
・「『多数派』の消滅」法学教室545号(2026年2月)1頁
VI 講演・報告
・「技術の精神 日本におけるフランスの法人論の受容について」(第3回中日研究者交流会,北海道大学)(2016年8月22日)
・ « L’autonomie et l’allégeance des salariés dans la société post-industrielle. A propos de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot », XIIème séminaire franco-japonais de droit public. (Hiroshima, 15, 15 et 17 mars 2018)
・「アラン・シュピオ教授との対話-『法的人間』から『数によるガバナンス』へ-(仏語)」(早稲田大学大学院法学研究科 公開講演会)(2019年6月5日)
・« Le principe de proportionnalité en droit constitutionnel » (10èmes journées franco-japonaises : Balance des intérêts (Tokyo,18 septembre 2019))
・« Le rôle de l’État social à l’épreuve de l’ouvrage d’Alain Supiot » (Manifestation organisée dans le cadre du programme SAKURA (JSPS) avec le soutien de Fondation Egusa.) (Tokyo, 20 septembre 2019)
・« Les droits de la personnalité face à la transformation numérique : du droit subjectif à l’institution objective », Forum franco-japonais “Nouvelles technologies et changements de paradigme en droit et en sciences politiques”, 8-9 Septembre, 2022, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, France
・« Gouvernance des risques lors de la crise sanitaire du point de vue du droit japonais », SÉMINAIRE DE RECHERCHE FRANCO-JAPONAIS CONCILIER SANTÉ ET DROITS FONDAMENTAUX EN PÉRIODE DE PANDÉMIE – UNE ANALYSE JURIDIQUE DES EXPÉRIENCES DE LA FRANCE ET DU JAPON – Paris-Lyon 22 et 23 septembre 2022
・« Développement historique de l’État de droit au Japon », XIVème Séminaire Franco-Japonais de Droit Public L’ÉTAT DE DROIT FACE À DES SOCIÉTÉS BOULEVERSÉES (Tokyo, 22 février 2023)
・« Rechtsstaat, Rule of law et bien-être public : discours de l’État de droit au Japon », XVème Séminaire Franco-Japonais de Droit Public (Luxembourg, 13 mars 2024)
・« La responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles au Japon et en France » (en collaboration avec C. GUERIN-BARGUES), LA RESPONSABILITÉ : Rencontres bilatérales de la Faculté de droit de l’Université de Tokyo et de l’Université Paris Panthéon-Assas (Paris, 20 septembre 2024)