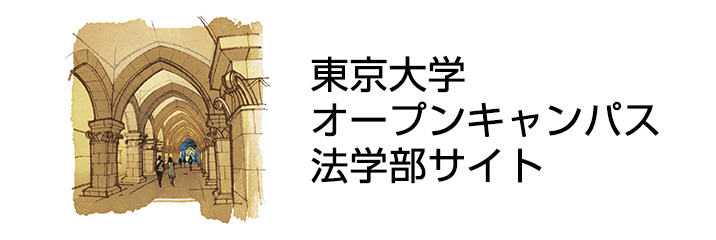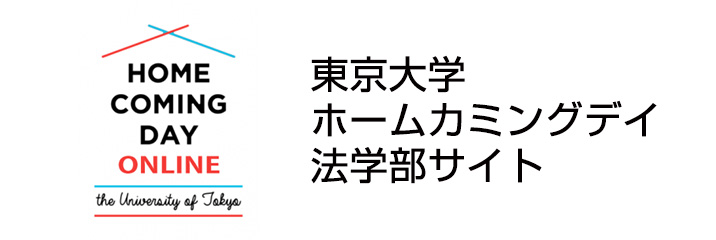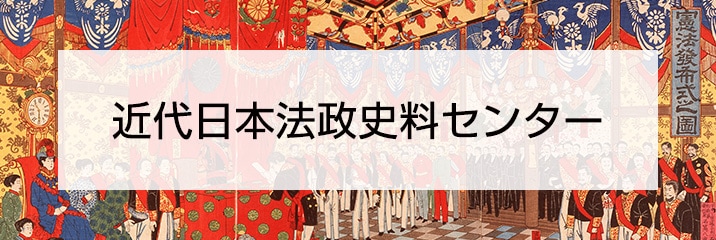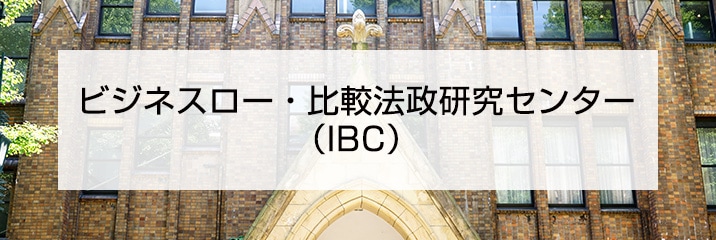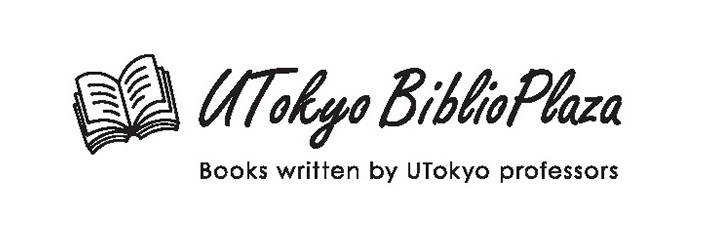中原 太郎(なかはら たろう)
教授
研究分野:民法
NAKAHARA TaroProfessor
Areas of Interest: Civil Law
略歴
2003年3月 東京大学法学部卒業(学士(法学))
2003年4月 東京大学大学院法学政治学研究科民法専攻修士課程入学
2005年3月 東京大学大学院法学政治学研究科民法専攻修士課程修了(修士(法学))
2005年4月 東京大学大学院法学政治学研究科助手
2007年4月 東京大学大学院法学政治学研究科助教(職名変更)
2008年4月 東北大学大学院法学研究科准教授
(2012年9月〜2014年8月 日本学術振興会海外特別研究員・パリ第1大学法学研究所客員研究員)
2018年10月 東京大学大学院法学政治学研究科准教授
2021年4月 東京大学大学院法学政治学研究科教授
関心分野
民法
担当授業科目
【学部】
民法第1部~第4部、消費者法、民法基礎演習、民法演習
【大学院】
基本科目民法1~3、上級民法1・2、消費者法、民事判例研究、民事系判例研究、民法演習
所属学会
日本私法学会、日仏法学会
連絡先
東京大学大学院法学政治学研究科・3号館受付
主要著作
【著書(共著・編著・共訳書)】
(1)『判例30!民法4債権各論』(有斐閣、2017年11月)(幡野弘樹・丸山絵美子・吉永一行との共著。執筆箇所:3~6、24~26、30~33、45~47、62~64、69~71、78~81、88~90、103~108、120頁)
(2)『現代独仏民事責任法の諸相』(商事法務、2020年3月)(編著。執筆箇所:3~29頁〔=論文(日本語)(20)〕、493~549頁〔=翻訳(9)〕)
〔紹介文URL:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/F_00001.html/https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/en/F_00001.html〕
(3) フランソワ・アンセル/ベネディクト・フォヴァルク=コソン『フランス新契約法』(有斐閣、2021年8月)(齋藤哲志との共訳書)
(4) 『民法6 事務管理・不当利得・不法行為〔有斐閣ストゥディア〕』(有斐閣、2022年8月)(山本敬三監修。根本尚徳・山本周平との共著。執筆箇所:1〜5、55〜129頁)
【論文(日本語)】
(1)「フランス法における申込み及び一方予約の拘束力とその基礎(1) (2・完)――契約成立前段階の法的規律に関する一考察――」法学協会雑誌123巻2号(2006年2月)335~418頁、3号(2006年3月)537~625頁
(2)「フランス」「ベルギー」「ルクセンブルク」「ケベック」『国際的な民法改正動向を踏まえた典型契約に関する調査研究報告書』(商事法務、2010年3月)39~243頁
(3)「機会の喪失論の現状と課題(1) (2・完)」法律時報82巻11号(2010年10月)95~100頁、12号(2010年11月)112~121頁
(4)「事業遂行者の責任規範と責任原理(1)~(10・完)――使用者責任とその周辺問題に関する再検討――」法学協会雑誌128巻1号(2011年1月)1~82頁、2号(2011年2月)271~360頁、3号(2011年3月)657~734頁、4号(2011年4月)849~909頁、5号(2011年5月)1105~1177頁、6号(2011年6月)1363~1437頁、7号(2011年7月)1659~1733頁、8号(2011年8月)1919~1950頁、129巻9号(2012年9月)2081~2179頁、10号(2012年10月)2366~2481頁
〔要旨:「事業遂行者の責任規範と責任原理――使用者責任とその周辺問題に関する再検討――」私法74号(2012年4月)169~176頁〕
(5)「国家賠償責任と使用者責任(1)~(3)――近時の国家賠償責任論が民法理論に示唆するもの――」法学74巻6号(2011年1月)677~714頁、75巻1号(2011年4月)1~38頁、77巻2号(2013年6月)85~125頁
(6)「原子力損害の填補・再論」現代民事判例研究会編『民事判例Ⅳ』(日本評論社、2012年4月)110~120頁
(7)「取締役の第三者に対する責任と不法行為責任」潮見佳男=片木晴彦編『民商法の溝をよむ』(日本評論社、2013年9月)199~206・215頁
〔原論文:「取締役の第三者に対する責任と不法行為責任」法学セミナー696号(2013年1月)10~13頁〕
(8)「福島原発事故と原子力損害の填補」稲葉馨=高田敏文編『今を生きる――東日本大震災から明日へ!復興と再生への提言――3 法と経済』(東北大学出版会、2013年2月)117~150頁
(9)「純粋経済損失」法律時報86巻5号(2014年5月)58~60頁
(10)「フランス民法典における『信託』について」水野紀子編著『信託の理論と現代的展開』(商事法務、2014年10月)253~386頁
(11)「過失責任と無過失責任――無過失責任論に関する現状分析と理論的整序の試み」現代不法行為法研究会編『不法行為法の立法的課題』(商事法務、2015年10月)33~57頁
(12)「代位責任の意義と諸相――監督義務者責任・使用者責任・国家賠償責任――」論究ジュリスト16号(2016年4月)41~49頁
(13)「福島原発事故により生じた損害の扱い」吉田克己=マチルド・オートロー=ブトネ編『環境リスクへの法的対応――日仏の視線の交錯』(2017年3月)73~87頁
(14)「不法行為責任における利益の階層性――フランス法主義の行方」日仏法学29号(2017年10月)65~96頁
(15)「フランスにおける『組織型契約』論の動向」河上正二=大澤彩編 『人間の尊厳と法の役割――民法・消費者法を超えて――〈廣瀬久和先生古稀記念論文集〉』(信山社、2018年12月)73~111頁
(16)「使用者責任と国家賠償責任――比較考察と横断的整理の試み」瀬川信久=能見善久=佐藤岩昭=森田修編『民事責任法のフロンティア〈平井宜雄先生追悼論文集〉』(有斐閣、2019年2月)433~472頁
(17)「シンポジウム 家族による財産管理とその制度的代替 6.中国」比較法研究81号(2020年2月)81~98頁・303~304頁(欧文要旨“China (Symposium : The property management by family and its alternatives)”)
(18)「フランスにおける遺言による財産承継の局面での交渉人の役割」法学83巻4号(2020年2月)561~583頁
(19)「日本法における権利濫用」民法研究第2集第8号〔東アジア編8〕(2020年3月)45~66頁
〔同一内容の論文を収録:「日本法における権利濫用」韓国民事法学85号(2018年12月)532~553頁〕
(20)「『機会の喪失』論の比較法的位相」同編著『現代独仏民事責任法の諸相』(商事法務、2020年3月)3~29頁
(21)「フランス法――遺言執行(者)の制度的前提――」道垣内弘人編著『各国における遺言執行の理論と実態〔トラスト未来フォーラム研究叢書85〕』(2020年5月)1~36頁(URL:http://trust-mf.or.jp/business/pdf/report/85.pdf)
(22)「民法分野における『利益の衡量』の諸相」『第10回日仏法学共同研究集会報告集「利益の衡量」(2019年9月17日〜18日東京)(ICCLP Publications No.15)』(2020年5月)33~44頁(URL:http://www.ibc.j.u-tokyo.ac.jp/publications/ICCLP_No.15.pdf(本文)/http://www.ibc.j.u-tokyo.ac.jp/publications/publications.html(目次))
(23)「純粋経済損失と不法行為法」法学教室478号(2020年7月)35~39頁
(24)「私法(実体法)」(〔特別企画〕第10回日仏法学共同研究集会)論究ジュリスト35号(2020年11月)200頁
(25) 「契約外責任(不法行為)法におけるフランス法主義とその変容――ベルギー法の改正動向(契約外責任法の改正に関する法律準備草案)を素材として――」NBL1183号(2020年12月)4~22頁
(26) 「間接被害者事例における直接被害者の過失の考慮」法学84巻3=4号(2020年12月)453~472頁
(27)「不法行為法――契約外責任の現代的展開と到達点」岩村正彦=大村敦志=齋藤哲志編『現代フランス法の論点』(東京大学出版会、2021年4月)189〜229頁
(28)「法定利率と中間利息控除」「安全配慮義務・安全配慮義務論」「債権者の担保保存義務」秋山靖浩=伊藤栄寿=宮下修一編著『債権法改正と判例の行方――新しい民法における判例の意義の検証』(日本評論社、2021年9月)61〜72・85〜96・194〜204頁
〔原論文:「債権者の担保保存義務」法律時報90巻1号(2017年12月)126~130頁/「安全配慮義務・安全配慮義務論」法律時報91巻5号(2019年4月)156~160頁/「法定利率と中間利息控除」法律時報92巻4号(2020年3月)123~127頁〕
(29) 「利益の吐き出し」「信託違反に関与した第三者の責任――認識受領と不誠実加功」能見善久編著『イギリス信託法の分析と示唆〔トラスト未来フォーラム研究叢書92〕』(トラスト未来フォーラム、2022年12月)85〜115・117〜147頁
(30) 「損害塡補制度としての補償基金に関する基礎的考察――クネチュの所説を中心に」沖野眞已=水野紀子=森田宏樹=丸山絵美子=森永淑子編『これからの民法・消費者法(Ⅰ)〈河上正二先生古稀記念論文集〉』(信山社、2023年3月)511〜549頁
(31) 「近時のフランスにおける『利益相反(conflit d’intérêts)』をめぐる議論――『利益相反』の体系的受容と一般法理化?」神作裕之編『フィデューシャリーデューティーの最前線』(有斐閣、2023年8月)264〜299頁
(32) 「不法行為法・不法行為責任と権利濫用〈点と点をつなぐ不法行為判例1〉」法学教室517号(2023年10月)64〜71頁
(33) 「第8章 有識者からのヒアリング」(インタビュアー・執筆)/「第9章 アンケート調査の実施」(構成)/「第10章 インタビュー調査の実施」(インタビュアー)/「第11章 デジタル化された遺言の想定利用者についての分析」(執筆)/「第12章 利用可能なデジタル技術について」(構成)『遺言制度のデジタル化に関する調査研究報告書』(商事法務研究会、2023年12月)209〜277頁
(34) 「被害者側の過失〈点と点をつなぐ不法行為判例4〉」法学教室520号(2024年1月)70〜77頁
(35)「寄与度に応じた責任〈点と点をつなぐ不法行為判例7〉」法学教室523号(2024年4月)55〜62頁
(36)「現代無過失責任論の一断面――AIシステムに起因する損害の塡補をめぐる議論を素材として」法律時報96巻7号(2024年6月)45〜51頁
(37)「土地工作物責任と営造物責任〈点と点をつなぐ不法行為判例10〉」法学教室526号(2024年7月)65〜72頁
(38)「フランスにおける原子力損害賠償法制――周辺問題も含む近時の動向を中心として」日本エネルギー法研究所編『原子力損害賠償法制の法的問題の諸相〔JELI R No.159〕』(日本エネルギー法研究所、2024年7月)77〜104頁
(39)「医療における協働関係の責任構造――チーム医療の推進動向を念頭におきつつ」潮見佳男先生追悼論文集(財産法)刊行委員会編『財産法学の現在と未来』(有斐閣、2024年9月)773〜797頁
(40)「人の死亡を契機とする財産承継を実現する信託と財産管理――特に公平義務・利益相反等について」能見善久編著『信託・信託法の直面する新課題に関する研究〔トラスト未来フォーラム研究叢書99〕』(トラスト未来フォーラム、2024年9月)15〜55頁
(41)「協働関係における過失判断――医療事故を素材として〈点と点をつなぐ不法行為判例13〉」法学教室529号(2024年10月)81〜89頁
(42)「『AIと民事責任』をめぐるヨーロッパの動向――『AIによるリスク』の定位」大塚直=米村滋人編『多様なリスクへの法的対応と民事責任』(商事法務、2024年10月)305〜349頁
(43) 「同性カップルの関係と不法行為法〈点と点をつなぐ不法行為判例17〉」法学教室533号(2025年1月)75〜83頁
(44)「離婚慰謝料の行方」大村敦志=窪田充見=久保野恵美子=石綿はる美編『家族法学の過去・現在・未来〈水野紀子先生古稀記念論文集〉』(有斐閣、2025年2月)395〜423頁
(45) 「不法行為責任と行為・危険・権利――潮見佳男『民事過失の帰責構造』」「継続的契約論の融解と昇華――中田裕康『継続的売買の解消』」吉永一行編『民法理論の進化と革新――令和に読む平成民法学の歩み出し』(日本評論社、2025年3月)261〜274・368〜380頁
【原論文:「不法行為責任と行為・危険・権利――潮見佳男『民事過失の帰責構造』」法律時報94巻1号(2021年12月)128〜133頁/「継続的契約論の融解と昇華――中田裕康『継続的売買の解消』」法律時報95巻8号(2023年7月)109〜114頁】
(46)「民法理論における『組織』の受容――契約・民事責任を題材として」大村敦志編『「人の法」研究序説』(有斐閣、近刊)掲載予定
【論文(外国語)】
(1) « Le principe de précaution et la responsabilité civile en droit japonais », in Y. LEQUETTE et N. MOLFESSIS (dir.), Quel avenir pour la responsabilité civile ?, Dalloz, juin 2015, p.105-116.
(2) « Le préjudice économique pur : rapport japonais », in Association Henri Capitant, IRDA et ARIDA, Le préjudice : entre tradition et modernité, Bruylant-LB2V, août 2015, p.53-73.
(3)「일본채권법 개정에 대한 연구」(日本語タイトル:「日本の債権法改正について」)韓国民事法学74号(2016年3月)347~362頁(AN, Moon Hee訳)〔注:Réforme de droit des obligations, 6èmes Journées franco-japonaises-coréennes de l’Association Henri Capitant, 28-29 août 2015, École de Droit de l’Université Nationale de Séoulでの報告原稿[Taro Nakahara, “Introduction générale à la réforme du droit japonais des obligations”]の翻訳〕
(4) « La responsabilité », in Bibliothèque de l’Association Henri Capitant, Droit du Japon, LGDJ, juillet 2016, p.79-85.
(5) « Le traitement du dommage nucléaire causé par l’accident de Fukushima », in M. HAUTEREAU-BOUTONNET et K. YOSHIDA (dir.), Regards juridiques franco-japonais sur le risque environnemental, PUAM, mars 2017, p.131-144.
(6) « Le risque « antenne-relais », regards pratiques de droit comparé. Rapport japonais », in M. HAUTEREAU-BOUTONNET et K. YOSHIDA (dir.), Regards juridiques franco-japonais sur le risque environnemental, PUAM, mars 2017, p.145-156.
(7)「债权让与――“日本法主义”及其现状」(日本語タイトル:「債権譲渡――『日本法主義』とその現況」)渠涛主編『中日民商法研究第16巻』(法律出版社、2017年9月)33~53頁(周江洪訳)
(8)「安全照慮義務的走向――民法(債権法)修改的一個層面」(日本語タイトル:「安全配慮義務論の行方――民法(債権法)改正の一断面」)渠涛主編『中日民商法研究第17巻』(法律出版社、2018年9月)151~165頁(渠遙訳)
(9)「關於權利濫用的備忘録」(日本語タイトル:「権利濫用に関する覚書」)渠涛主編『中日民商法研究第18巻』(法律出版社、2019年9月)131~144頁(渠遙訳)
(10) « Les opérations translatives. Rapport japonais », in K. Baba, F. Bicheron, R. Boffa, B. Haftel, M. Mekki, T. Saito et K. Yamashiro (dir.), Droit civil japonais : Quelle(s) réforme(s) à la lumière du droit français, LGDJ, juillet 2020, p.101-117.
(11) « Les préjudices réparables résultant du dommage corporel lié à la Covid-19 en droit japonais de la responsabilité civile », Les cahiers Louis Josserand n°3, juillet 2023(URL : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97974212-edition-n-3-du-27072023#article-486407).
(12)「『機会喪失論』在比較法上的差異」(日本語タイトル:「『機会の喪失』論の比較法的位相」)渠涛主編『中日民商法研究第19巻』(法律出版社、2023年10月)97〜111頁(渠遙訳)
(13) « Les mutations de la causalité en matière épidémiologique : regard de droit japonais », in B. Parance et J. Rochfeld (dir.), Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, Dalloz, juin 2024, p.103-108.
(14)「AI와 민사책임 – 일본에서의 논의와 현황」(日本語タイトル:「AIと民事責任――日本における議論の現況」)韓国民事法学109号(2024年12月)447〜504頁(KIM, Ji Young訳)
(15) « Responsabilité civile et intelligence artificielle : état actuel du droit japonais », Revue internationale de droit comparé 77e année, n°1/305°, janvier 2025, p.59-72.
(16) « Les différents aspects de la « balance des intérêts » en droit civil », in Balance des intérêts. 10èmes rencontres franco-japonaises, Société de législation comparée, à paraître.
【注釈】
(1)「709条」「710条」「711条」能見善久=加藤新太郎編『論点体系 判例民法8不法行為Ⅰ〈第3版〉』(第一法規、2019年8月)1~52・53~59・60~64頁
(2)「715条」「716条」大塚直編/大村敦志ほか編集代表『新注釈民法(16)』(有斐閣、2022年9月)69〜208・208〜225頁
(3)「法律行為の解釈」「91条」「92条」鎌田薫=佐久間毅=小粥太郎編『新基本法コンメンタール 民法 民法総則』(日本評論社、近刊)掲載予定
【座談会】
(1)「座談会 インターネット上の表現に関する名誉毀損訴訟・発信者情報開示訴訟」論究ジュリスト21号(2017年4月)110~133頁(道垣内弘人〔司会〕=山本和彦=小粥太郎=中原太郎=岸日出夫=山田真紀=朝倉佳秀=武部知子)
(2)「第10回日仏法学共同研究集会・座談会『利益の衡量』」論究ジュリスト35号(2020年11月)184~198頁(森田宏樹〔司会〕=大村敦志=垣内秀介=北村一郎=小島慎司=齋藤哲志=瀬川信久=中原太郎=三浦大介=亘理格)
【判例評釈】
(1)「最高裁判所民事判例研究(民集57巻4号)1.現金自動入出機(ATM)による預金の払戻しと民法478条の適用の有無 2.無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというための要件 3.無権限者が預金通帳を使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて銀行に過失があるとされた事例(最高裁平成15.4.8判決)」法学協会雑誌122巻10号(2005年10月)1771~1795頁
(2)「最高裁判所民事判例研究(民集57巻11号)1.戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否 2.戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字を子の名に用いることの可否(平成15.12.25第三小法廷決定)」法学協会雑誌122巻11号(2005年11月)1957~1974頁
(3)「労災保険法に基づく遺族補償年金の給付と損益相殺的調整」法学教室425号(別冊判例セレクト2015Ⅰ)(2016年2月)20~20頁
(4)「運行によって(4)――集中豪雨による冠水道路での走行不能車両からの避難に際しての溺死」新美育文=山本豊=古笛恵子『交通事故判例百選〈第5版〉』(有斐閣、2017年10月)34~35頁
(5)「企業損害」森嶌昭夫監修・新美育文=加藤慎太郎編集『実務精選100 交通事故判例解説』(2017年12月)94~95頁
(6)「使用者から被用者への求償権の制限」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ〈第8版〉』(有斐閣、2018年3月)192~193頁
【旧版:「使用者から被用者への求償権の制限」中田裕康=窪田充見編『民法判例百選Ⅱ〈第7版〉』(有斐閣、2015年1月)184〜185頁】
(7)「民法上の名誉毀損と真実性・相当性の抗弁――『署名狂やら殺人前科』事件」長谷部恭男=山口いつ子=宍戸常寿編『メディア判例百選〈第2版〉』(有斐閣、2018年12月)52〜53頁
(8)「不倫と不法行為責任」加藤新太郎=前田陽一=本山敦編集『実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説』(第一法規、2019年5月)24〜25頁
(9)「子の名に用いることができる文字」加藤新太郎=前田陽一=本山敦編集『実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説』(第一法規、2019年5月)116〜117頁
(10)「違法な仮差押命令の申立てと債務者に生じた逸失利益の損害との間の相当因果関係」私法判例リマークス61号(2020年7月)46〜49頁
(11)「浮貸しと銀行の使用者責任」金融法務事情2145号(金融判例研究30号)7〜10頁(2020年9月)
(12)「破産管財人による不当利得返還請求に対する不法原因給付の主張の可否」松下淳一=菱田雄郷編『倒産判例百選〈第6版〉』(有斐閣、2021年1月)42〜43頁
(13)「複数の公務員が連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合」私法判例リマークス61号(2021年7月)42〜43頁
(14)「最高裁判所民事判例研究(民集74巻4号)後遺障害逸失利益の定期金賠償の可否と終期(最高裁令和2.7.9判決)」法学協会雑誌139巻5号(2022年5月)472〜509頁
(15)「医療事故責任における高度の注意義務と医療水準」甲斐克則=手嶋豊編『医事法判例百選〈第3版〉』(有斐閣、2022年7月)90〜92頁
(16)「児童養護施設における事故と損害賠償責任」斎藤誠=山本隆司『行政判例百選Ⅱ〈第8版〉』(有斐閣、2022年11月) 464~465頁
【旧版:「児童養護施設における事故と損害賠償責任」宇賀克也=交告尚史=山本隆司『行政判例百選Ⅱ〈第7版〉』(有斐閣、2017年11月)476~477頁/「児童養護施設における事故と損害賠償責任」宇賀克也=交告尚史=山本隆司編『行政判例百選Ⅱ〈第6版〉』(有斐閣、2012年11月)490〜491頁】
(17)「代表理事の代表権の制限と民法110条」潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〈第9版〉』(有斐閣、2023年2月)62〜63頁
【旧版:「代表理事の代表権の制限と民法110条」潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〈第8版〉』(有斐閣、2018年3月)64~65頁/「代表理事の代表権の制限と民法110条」潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〈第7版〉』(有斐閣、2015年1月)64〜65頁】
(18)「責任能力を欠く認知症高齢者の行為と民法714条――JR東海事件」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ〈第9版〉』(有斐閣、2023年2月)168〜169頁
【旧版:「認知症患者の起こした事故と家族の責任――JR東海事件」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ〈第8版〉』(有斐閣、2018年3月)188~189頁】
(19)「被用者から使用者への『逆求償』」窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ〈第9版〉』(有斐閣、2023年2月)172〜173頁
(20)「ボランティアの民事責任」岩村正彦=水島郁子=笠木映里編『社会保障判例百選〈第6版〉』(有斐閣、2025年2月)220〜221頁
【旧版:「ボランティアの民事責任」岩村正彦編『社会保障判例百選〈第5版〉』(有斐閣、2016年5月)208〜209頁】
【翻訳・文献紹介】
(1)「学界展望〈フランス法〉Anne Guégan-Lécuyer, Dommages de masse et responsabilité civile」国家学会雑誌125巻11=12号(2012年11月)129~132頁
(2) ヴァレリオ・フォルティ「コモン・ロー体系におけるトラストがフランスのフィデュシに及ぼす影響」水野紀子編著『信託の理論と現代的展開』(商事法務、2014年10月)237~251頁
(3) ヨナス・クネチュ(ジョナス・クネシュ)「講演 フランス民事責任法改正――2016年4月29日の司法省法律草案の比較法的検討」法学80巻5号(2016年12月)555〜580頁
(4)「資料 民事責任の改正に関する法律草案(フランス司法省・2016年4月29日)」法学80巻5号(2016年12月)581〜598頁
(5) エヴ・トルイエ=マランゴ「法における科学的不確実性の扱いに関する多角的検討――EU法における不確実なリスクの扱い」吉田克己=マチルド・オートロー=ブトネ編『環境リスクへの法的対応――日仏の視線の交錯』(2017年3月)9~28頁
(6)「資料 フランス民事責任法改正に関する2つの草案(カタラ草案・テレ草案・規定対照表)」法学81巻1号(2017年4月)24~55頁
(7) パトリス・ジュルダン/アンヌ・ゲガン=レキュイエ/ジョジアンヌ・キャリエール=ジュルダン「講演 シンポジウム フランス不法行為法の現代的課題――環境損害・多衆侵害」法学82巻2号(2018年6月)149~186頁
(8) マチルド・オートロー=ブトネ/ヴァンサン・オートロー「講演 環境に対する侵襲――フランス民事責任法をどう変身させるか?」法学82巻3号(2018年8月)311~335頁
(9) パスカル・アンセル「講演 ドイツ法の観点から見たフランスおよびベルギーの民事責任法改正」(含:「民事責任改正案――2017年3月」(フランス司法省・2017年3月13日)、「新民法典に契約外責任に関する規定を挿入する法律準備草案」(ベルギー責任法改正委員会・2017年9月30日))中原太郎編著『現代独仏民事責任法の諸相』(商事法務、2020年3月)493~549頁
(10) パスカル・アンセル「講演 フランス新債権法における契約の拘束力」東京大学ビジネスロー・ワーキングペーパー・シリーズNo.2020-J-02(2020年7月)1~20頁(URL:https://www.j.u-tokyo.ac.jp/research/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/BLWPS2020J02_Ancel.pdf(本文)/https://www.j.u-tokyo.ac.jp/research/blwps/(目次))
(11)ヨナス・クネチュ「Covid-19ワクチンの接種に関する責任」民法研究第2集10号〔フランス編1〕(2024年1月)65〜87頁
*中原太郎「〈セミナー〉Covid-19に関する責任の諸態様――企画趣旨」民法研究第2集10号〔フランス編1〕(2024年1月)1〜2頁
*住田守道=中原太郎「ポルシィ=シモン報告およびクネチュ報告について」民法研究第2集10号〔フランス編1〕(2024年1月)88頁
(12) ローラン・ルヴヌール「Covid-19による衛生危機とフランス契約法」水野紀子=大村敦志編『フランス民法の伝統と革新Ⅰ――総論と家族・債務』(信山社、2024年6月)253〜267頁
(13) オリヴィエ・グー「医療の環境におけるCovid-19への感染――ONIAM(医療事故等全国補償局)の関与」/ヨナス・クネチュ「補償基金によるCovid-19ワクチンに関する損害の負担引受け」/ステファニ・ポルシィ=シモン「Covidへの感染のケースにおける賠償可能な損害」民法研究第2集12号〔フランス編3〕(2025年2月)5〜18・19〜36・57〜67頁
*中原太郎「〈セミナー〉Covid-19危機による損害の塡補――企画趣旨」民法研究第2集12号〔フランス編3〕(2025年2月)3〜4頁
*中原太郎「グー報告およびクネチュ報告について」民法研究第2集12号〔フランス編3〕(2025年2月)37頁
*中原太郎「ポルシィ=シモン報告について」民法研究第2集12号〔フランス編3〕(2025年2月)68頁
【解説】
(1)「暴力団組長の使用者責任」「過労自殺と使用者責任」「事業執行性:取引的不法行為(1)」「事業執行性:取引的不法行為(2)」「事業執行性:事実的不法行為(1)」「事業執行性:事実的不法行為(2)」「第三者の使用者に対する求償」「使用者間の求償」「使用者の被用者に対する求償」潮見佳男=山野目章夫=山本敬三=窪田充見編『新・判例ハンドブック【債権法Ⅱ】』(日本評論社、2018年4月)228・229・230・231・232・233・234・235・236頁
(2)「情報提供者の責任/郵政民営化通信事件」「ニュース・ポータルサイト運営者の責任/ヤフーニュース事件」「迷惑メールの送信と差止め/ニフティダイレクト・メール事件」「迷惑メールの送信と損害賠償/ドコモ宛先不明メール事件」「消費者契約法12条1項・2項にいう『勧誘』の意義/クロレラチラシ事件」「インターネット・オークション(1):売主の責任/中古アルファロメオ事件」「インターネット・オークション(2):運営者の責任/ヤフオク集団訴訟事件」「インターネット・ショッピング/ヤフーショッピング事件」「インターネットによるFX取引/外為どっとコム誤ティック事件」宍戸常寿編著『新・判例ハンドブック【情報法】』(日本評論社、2018年11月)81・82・163・164・165・182・183・184・185頁
(3)「遺産分割協議の法定解除」「遺産分割協議の合意解除」松本恒雄=潮見佳男=羽生香織編『判例プラクティス民法Ⅲ〈第2版〉』(信山社、2020年12月)151頁・152頁
【旧版:「遺産分割協議の法定解除」「遺産分割協議の合意解除」松本恒雄=潮見佳男編『判例プラクティス民法Ⅲ』(信山社、2010年8月)143頁・144頁】
(4)「未成年者と監督義務者の責任」千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice Ⅱ 債権編〈第5版〉』(商事法務、2022年10月)341~349頁
【旧版:「責任能力と監督義務者責任」千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice Ⅱ 債権編〈第4版〉』(商事法務、2018年6月)338~346頁/「責任能力と監督義務者責任」千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice Ⅱ 債権編〈第3版〉』(商事法務、2017年3月)300〜308頁】
(5) 「利息概念と法定利率」「安全配慮義務」「監督義務者責任(1)――未成年者」「監督義務者責任(2)――精神障害者」「使用者責任」「使用者・被用者間の求償」「土地工作物責任」沖野眞已=窪田充見=佐久間毅編著『民法演習サブノート210問〈第3版〉』(弘文堂、2025年4月)149~150・151~152・313~314・315~316・317~318・319~320・321~322頁
【旧版:沖野眞已=窪田充見=佐久間毅編著『民法演習サブノート210問』(弘文堂、2018年7月)149~150・151~152・313~314・315~316・317~318・319~320・321~322頁/沖野眞已=窪田充見=佐久間毅編著『民法演習サブノート210問〈第2版〉』(弘文堂、2020年11月)149~150・151~152・313~314・315~316・317~318・319~320・321~322頁】
【その他】
(1)「フランス不法行為法の現代的諸相――伝統と革新の間で――」東北法学会会報33号(2015年6月)1~3頁(URL:http://www.law.tohoku.ac.jp/research/thg/nakahara.pdf)
(2)「日本における民商法の関係」第7回日台アジア未来フォーラム・第5回台北大学飛鳶法学国際学術シンポジウム『台・日・韓における重要法制度の比較――憲法と民法を中心として』(国立台北大学法律学院・SGRA、2017年5月)140〜146頁
(3)「3論文の日本における意義――総括的コメント」大村敦志編『東アジアにおける日本法研究の意義(第2回 東アジア大学院生・民法国際セミナー報告書)』(東京大学法学部大村敦志研究室、2017年6月)51〜58頁
〔注:「3論文」=渠涛「中国における市場経済化と契約法の整備」私法57号(1995年)/権澈「遺言による財団設立――フランス法におけるfondation post-mortem論を中心に」東京大学大学院法学政治学研究科博士論文(甲第22905号。2007年7月12日博士号付与)/黄詩淳「台湾法での相続の過程における遺留分減殺請求の機能(1)〜(4)完」北大法学論集57巻4号〜58巻1号(2006〜2007年)〕
(4)「東北大学をつくった人々⑥――中川善之助」まなびの杜84号(2018年6月)5頁(URL:http://www.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi84/manabi84.pdf#page=6)
(5) « L’appréhension du lien de causalité au regard de l’épidémiologie : L’expérience en droit japonais de la responsabilité civile », in Cour de cassation, Conférences-Cycle 2022 : Les grands notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, 2ème Conférence : Faut-il modifier l’appréhension du lien de causalité ?, 31 mars 2022(URL:https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/environnement-faut-il-modifier-lapprehension-du-lien-de-causalite〔登壇箇所:1:34:20〜1:48:30〕).
(6)「定期金賠償――最判令2・7・9(最高裁判所民事判例集74巻4号1204頁)とその含意」日本エネルギー法研究所月報276号(2022年6月)1〜3頁(URL: https://www.jeli.gr.jp/img/file93.pdf)
(7)「《早慶合同ゼミナール》人身侵害に関する諸問題――ギグワーカー・同性パートナーを素材として」法学教室511号(2023年3月)140〜147頁(田髙寬貴・白石大との共著。執筆箇所:143〜147頁)