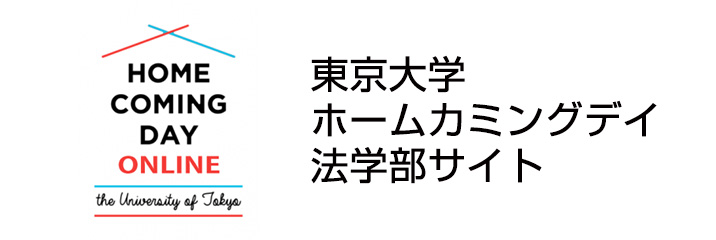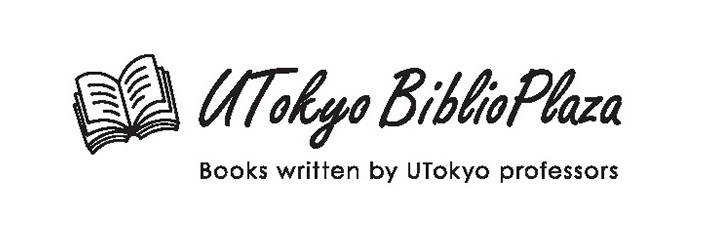コラム30:末弘厳太郎博士のことば
大正・昭和期の法学者であった末弘厳太郎博士(1942-45年、東京帝大法学部長)は、『法律時報』9巻4号(1937年4月)に寄稿した「新たに法学部に入学された諸君へ」という短い文章の中で、法学初学者に対する注意事項を述べている。今から80年近く前に書かれたこの文章は、驚くべきことに、現代の法学初学者に対してもそのまま適切な助言となっている。
末弘博士はまず、法学初学者が直面する困難の原因として、他の諸学部の場合とは異なり、大学入学以前に法学の何たるかを知って法学部に入学してくる学生がほとんどいないことを指摘したうえで、そのことが、法学部の学生が法学教育の目的を誤解してしまい、適正な学習態度を身に付ける妨げになっている、と述べている。具体的には、学生が、法学という学問を法典や条文の知識を覚えるものだと軽く考えてしまう結果、高校までの勉強と同じように暗記を中心とした学習を行うようになることが、法学の理解を妨げ、法学嫌いを生み出している、というのである。
法学研究の落ちこぼれである私が言うのもおこがましいが、この指摘は、現代の法学嫌いの学生についても大いに当てはまると思う。法学の勉強が合わない、嫌いだ、という学生の中には、法学という学問が主観的で客観性に欠ける、という指摘をする人がいる。確かに、法解釈には常に価値判断や評価がつきまとうから、仮に自然科学的な客観性を学問の規範と見なすならば、法学が主観的な学問であるように見えるのもわからなくはない。しかし、「客観性に欠ける」という発言の裏には、「客観的な正解がないから、何を信じていいのかわからない」、という寄る辺ない心情が横たわっていることに気づくようになった。つまり、彼らにとって「正解」とは自分の外に客観的に存在しており、権威者の示す「正解」を覚えることが「正しい勉強法」だと思い込んでいたのであろう。考えてみれば、高校までの勉強においては、そのような勉強方法がむしろ一般的だったかもしれない。自分の頭で考えることが必要であったとしても、あくまでそれは「正解」に到達するための手段であって、正解自体はあらかじめ所与のものとして存在しているはずであった。もしもこのような学習態度のまま法学の学習に向かったならば、ある条文の解釈につき、A説、B説、C説という3つの学説が対立しているが、判例・通説はB説である、といった事実を、ただ機械的に覚えようとするかもしれない。このような学習態度では法学の勉強が無味乾燥でつまらないものになってしまうのは必然であろう。
末弘博士も述べておられるように、学説の間に相違があるのは、その相違を生み出すべきそれぞれの理由があるのだから、その理由にまで遡って各学者の考え方を研究しなければならない。そうでなければいたずらに物識りになるだけで、法律的に物事を考える力がつかない。しかし、法学教育の最大の目的は、まさにこの「法律的に物事を考える力」のある人間を作ることであり、法律専門職につくわけではない多くの学生が社会に出た後で真に役立つものも、現行法に関する知識であるよりは法学的思考である、と末弘博士は言う。
末弘博士はまた、「学生として一番おそれなければならないのは、自分ではわかったつもりでいて、実は講義の真意を理解していないようになることであって、入学の当初になまけると、とかくこういうことになりやすい。人間というものは、他人の言うことを聞いても、本を読んでも、自分の力相応にしか理解し得ないものである」とも述べている。ああ、耳が痛
い。
なお、末弘博士は1951年、『法律時報』23巻4・5号に寄せた「法学とは何か――特に入門者のために」という文章の中でも、ほぼ同様のことをさらに敷衍しつつ述べている。これらの文章はいずれも末弘厳太郎(佐高信〔編〕)『役人学三則』(岩波現代文庫)の中に収録されているので、法学の学習方法に疑問を感じた方は是非一読されることをお勧めする。
(文責:稲田)