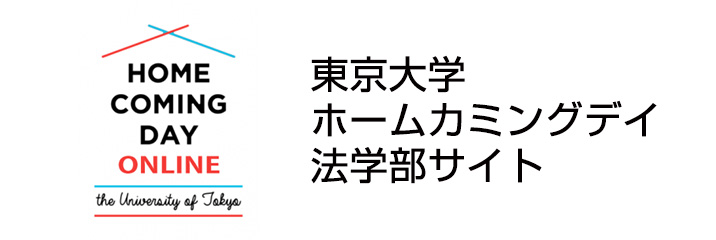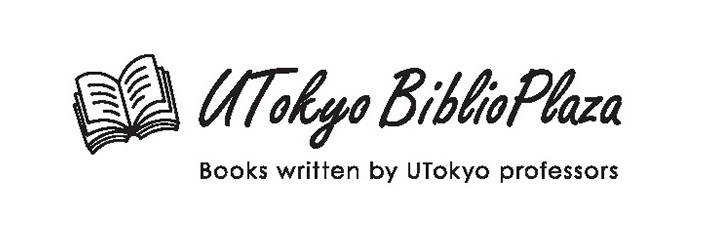コラム40:鳥の自由と法律家の自由
法学政治学研究科・法学部教授 垣内秀介
1 法学初学者の悩み
大学での勉強は高校までとは異なる、とよく言われるが、筆者のみるところ、法学は、このことがとりわけよく当てはまる学問分野である。何より、高校までの科目には、法学に直接対応するものが存在せず、大学入学前にその内容を想像することは困難である。その上、実際に法学を学び始めると、その内容は、それまで経験してきたものとは大いに異なる、という印象を受けることが一般的である。その結果、少なからぬ学生が、法学をどのように勉強したらよいのか、さらには、法学を学ぶとはいったいどういうことなのか、どんな意味があるのか、という疑問を抱え込むこととなる。
筆者は、こうした疑問を抱くことは全く正当なことであり、むしろ、法律家としての適性を示す一つの徴表であるとさえ言い得ると考えている。それだけに、こうした疑問に直面した学生が、そのために法学を学ぶことを断念するようなことがあるとすれば、残念なことである。そこで、以下では、法学を学ぶことの意味について、筆者がこれまで考えてきたことを述べてみることにしたい。
2 法学についての分裂したイメージ
筆者自身の体験も思い起こしながら考えてみると、初学者がそうした悩みを抱く原因の一つとして、法学を学ぶことについて、2つの全く異なるイメージが存在する、ということが挙げられるように思われる。
すなわち、一方で、法学とは、要するに法令の条文や裁判例の暗記に尽きるのではないか、というイメージが存在する。法学を実際に学ぶ前の段階においては、このようなイメージが支配的なのではないかと思われる(実際、筆者の同級生の中には、たとえば民法の条文を1条からすべて暗唱しようする者がいた)。しかし、もしそうだとすれば、法学とは、およそ高度に知的な営為とは考えにくく、大学でそのような勉強をすることにどのような意味があるのか(予備校でよいではないか)、という深刻な疑問が生じるところである。
これに対して、他方で、法学部の教員の話や法学初学者向けの各種の文章をみると、法学の勉強とは決して条文や判例の暗記ではないことを強調するものが少なくない。むしろ、法学における結論とは、条文や判例の巧みな操作によってどちらとも言えるものであり、まさに「正解」はないのであって、一番大事なのは「自分の頭で考える」ことだというのである。こうした見方からは、法律家としての思考力・判断力の重要性(「リーガル・マインド」)が強調され、法学の勉強とは、これを身につけることだといわれることになる。しかし、学生の立場に立ってみると、いったいどうすればこのような能力が身につけられるのかは明らかでない。日々の授業を聴講していても、結論の導出を論証・正当化するプロセスは、仮に条文や先例に依拠しないとすれば、ごく常識的な論理や、「比較衡量」といった客観化の困難なものが多く、これが果たして「学問」の名に値するのか(極端に言えば、論者の立場次第で何とでも言えるのではないか)、といった疑念にさらされる。しかも、試験を受けてみれば、実際には、基本的な用語・概念や重要問題に関する判例・通説などをきちんと記憶していないと、まともな答案を作成することは覚束ないことに気づくのである。
3 法学教育の目標
それでは、法学を学ぶということについて、いったいどのように捉えたらよいのであろうか。
結論から言えば、筆者は、法学教育の目標は、自由な判断主体としての法律家というものを育てることにある、と考えている。もっとも、ここで「自由」というのは、たとえば、「鳥は空を自由に飛べていいな」というときの「自由」とは異なる。というのも、鳥は、自ら自由に判断して空を飛んでいると言えるであろうか。むしろ、現実を知覚し、本能に従って、それを無媒介に行動に反映させているだけではないだろうか。そうだとしたら、そこに自由な主体というものは存在するだろうか。
このように考えると、ここで鍵を握るのは、言語の作用だといえる。言語によって現実を解釈し、そこからいったん距離を置く、というときに、はじめて、その主体としての「自分」というものが現れる、と考えられるからである(ちなみに、今の学生の皆さんにとっては懐メロの類いかもしれないが、宇多田ヒカルにAutomaticという名曲がある。法律家の視点からすると、この曲は、感覚や身体が”automatic”だと歌うことによって、それを歌っている自己が析出されてくるところに意義がある。宇多田ヒカルには、法律家の素質があるに違いない)。
ひるがえってみると、法学とは、まさに、言語で構成されたルールと、さまざまな利害や欲望が渦巻く現実との間の緊張関係を扱う営為である。とすれば、法律家にとって、言語の使い方に習熟する必要性は、ほとんど自明のことである。法律家が、言葉の論理の一貫性や、概念の厳密な定義にこだわるのは、決して理由のないことではない。これらは、現実の利害が論証に無媒介に侵入することを防ぐための防壁の役割を果たすからである。国によって程度の差はあるものの、法学が一貫した理論体系というものを構築しようとする理由の一端も、ここにあると考えられる。
とはいえ、もちろん、言語さえ用いれば当然に上記のような意味での「自由」が保障されるというわけではない。ものは使いようであり、一口に言語といっても様々な使い方があるからである。たとえば、誰かに命じられたことに反射的に従う、とか、論証パターンのようなものを覚え込んで、どんな問題が来ても反射的に「正解」をはき出す、というときに、そこに自由な主体がいるとは考えられない。このことは、与えられたプログラムの通りに動くコンピュータを自由な主体と呼ぶことができるか、ということを考えてみれば理解できよう。たしかに、このような言語の使い方、すなわち、言語で提示された内容について何の解釈を差し挟むこともなく自動的に反応を返す、という使い方は、大いに効率的なものではあるから、時と場合によっては必要であるし、とかく現代は効率性が重視される時代でもある。そこでは、一々立ち止まって言葉の意味を吟味する法律家は、煙たい存在かも知れない。しかし、法学教育の目標は、インプットに対して一様に「正しい」アウトプットを返してくる優秀なコンピュータを生産することにあるわけではない。むしろ、時に煙たいと思われようとも、その時その時の現実に無批判に流されたり(「空気」の支配による個人の圧殺)、上司や依頼者の指示に無批判に従う、というのではない、というところに、法律家というものの存在意義が認められるのである。そして、現実の変化や新たな問題に対応することも、こうした自由な主体が存在することによって、初めて可能になる。
4 勉強のしかた
このようにみてくると、法律家として最低限備えるべき資質は、一方で、現実に対して十分に批判的であるとともに、他方で、批判の道具となるべき言語そのものについても批判的である、という点に見出すことができる。そして、2で述べた法学の勉強に関する2つのイメージは、それぞれこれらの側面に対応している。
すなわち、前者の側面からすれば、法学が依拠する言語体系の習得が不可欠であり、これは、暗記の要素を多分に含んでいる。これは、外国語の習得の際に、まずは単語や文法を覚える必要があるのと同じである。これは、特に初期の段階では、無味乾燥とも感じられようが、やむを得ないところがある。まず言葉を知らなければ、それを使って自由に議論することもできないからである。
他方で、法学の勉強が暗記に尽きるものでないことは、後者の側面に対応する。決して「何でもあり」というわけではなく、法学という言語の概念や文法を踏まえたものである必要はあるが、それぞれに独立の主体として議論に参加することが求められるからである。その意味で、まずは法学を自分の言葉にする、その上で、それを突き放す、ということが求められるのである。
5 おわりに
以上は筆者個人の試論にすぎず、他の法学部の教員は、それぞれ違った考えを持っていることであろう。読み手の皆さんにとっても、こうした考えをどのように受け止めるかは、もちろん自由であるが、これが法学を学ぶことの意味を考える際の何かの材料にでもなることがあれば、筆者としては幸いである。
最後になるが、皆さんのご健闘を祈るとともに、進学先として法学部を選んだ、あるいはこれから選ぶであろう方々に対しては、心から歓迎の意を表したい。
(初出は「進学情報センターニュース No. 65」です。転載を快く許可して下さいました「東京大学教養学部進学情報センター」には心より御礼申し上げます。)