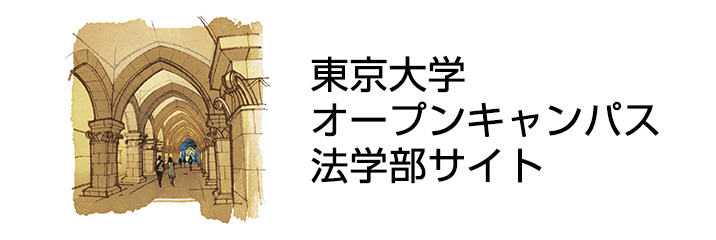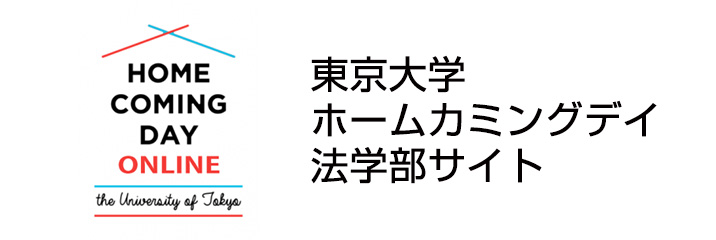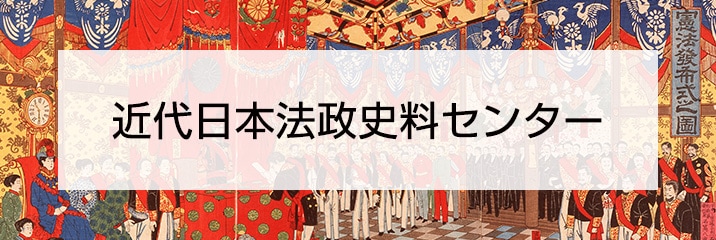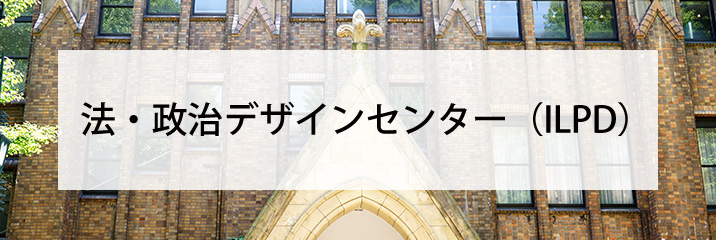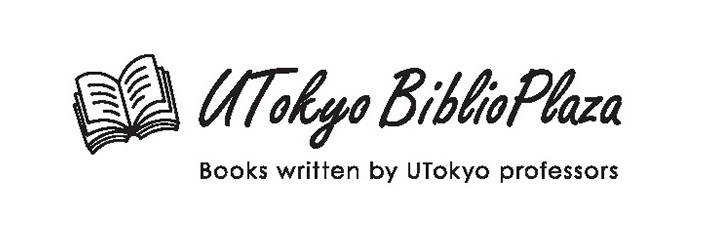4月…新生活の時期ですね。私もこの4月から学習相談室の心理カウンセラーとして新しい生活をはじめます。今回は、私の勤務初日の逡巡をお伝えしようかな…と思います。
心理相談スペースは、「法文1号館4階B5演習室向かい」というちょっと行きにくい場所にあります。看板も「学習相談室」となっていて分かりにくいかもしれません。そして、重めのドアには、窓が全くありません。(カウンセリング・スペースとしては、とても安心できる設計です。)外側には、白い札がかかり、その札には「開室中」と記載されています。「開室中」と記載されているものの、ドア自体は閉まっていますし、わざわざノックをして入る必要があります。
「ドアは開けておいた方がいいのかな」
「でも、相談はまだオンラインだけの対応だよね」
「ドアが開いたままだったら、安心して話せる場所だとは思ってもらえないかな」
「ドアを開けているのに、今はまだ対面の面談は難しいとお伝えしたら、がっかりかな…」
先輩の心理カウンセラーにも尋ねてみました。普段は「閉めている」とのこと。
「でも、外から見られないと、私がどんな人か伝わらないなぁ」
「そういえば、昔、目つきだけは怖いって言われたことある」
「外を歩く人と目が合ったら気まずいよね」
「せっかくだから、パンフレットをもらっていってほしいな。たくさん役に立つことが書いてあるし。」
いろいろと考えていた勤務初日でした。
***
話題はガラリと変わってアイデンティティのお話になります。通俗書や文学作品では「自分らしさ」や「私らしく生きること」と説明されることが多く、漢字では自我同一性と記される比較的よく知られた概念です。中高の授業や、大学の心理学の授業でもお馴染みで、青年期の発達課題としてよく触れられる”あの言葉”です。
よく知られる言葉ですが、それについて記したエリクソンの著作は非常に難解です。「厳密に著作を読むとエリクソン自身はアイデンティティの定義をしていない」と主張する心理学者すらいるくらいです。(エリクソンは「アイデンティティ」を定義しておらず、「アイデンティティの感覚」を定義しているのだそうです。)
エリクソンは、アイデンティティの感覚について、自己斉一性、対自的同一性、対他的同一性、心理社会的同一性を挙げています。自己斉一性と対自的同一性は、自分に関する同一性の感覚です。これは、中高の授業で習うアイデンティティとそう矛盾しないものです。しかし、エリクソンは、それらに「対他的同一性(他者から見られているであろう自分と自分自身が思う本来の自分が一致している感覚)」と「心理社会的同一性(現実社会に自分を適応的に関連づけられている感覚)」を加えています。つまり、アイデンティティの感覚とは、周囲や社会からの見られ方も加えた同一性の感覚だということです。大胆に矮小化してしまえば、アイデンティティの感覚を保つためには、「自他双方から」の視線への意識が求められます。「自分」について考える時には、しばしば自己や自我に偏りがちです。けれども、アイデンティティの達成には、そして青年期の発達課題を達成するためには、「他からの見られ方」について意識することも同じくらい重要となるのです。
***
冒頭の私の逡巡に戻ります。新任の私が「法学部の学習相談室の心理カウンセラーだ」と思えるためには、つまりは、心理カウンセラーとしてのアイデンティティの感覚を保つためには、法学部の皆様からの視線を意識することも必要だと考えました。そして、いささか乱暴ですが、法学部の皆様に心理相談スペースの中まで見てもらえるようにして、皆様からの視線を直接的に感じるという方法を思いつきました。そこで、手始めとして、講義と講義の間の休み時間やお昼休みの一部には、ドアを開けて、在室中の私を見てもらえるようにしておこうと思います。B5演習室の近くを通った際に、もしドアが開いていたら、そっと中をのぞいてみてください。目つきだけは怖い相談員が座っているかもしれません。
ps. もちろん、秘密を守るため、ご相談中や電話中はドアはしっかりと閉めておきます。
(文責:神谷)