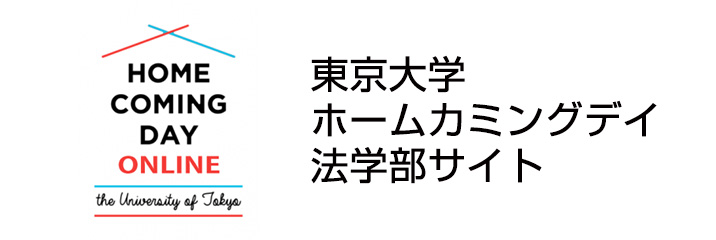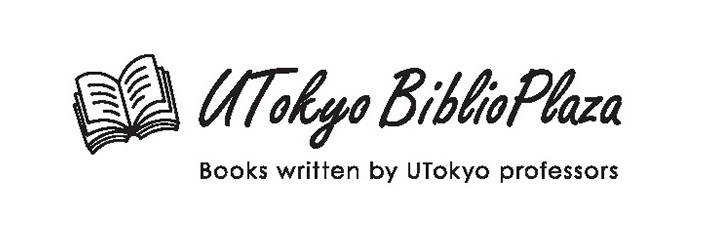コラム41:浅井君の勘違い
法学政治学研究科・法学部教授 木庭顕(元学習相談室運営委員長)
夏目漱石「虞美人草」(1907年)の著名な一節を引く(*)。
浅井君は遠慮のない顔をして小夜子を眺めている。これからこの女の結婚問題を壊すんだなと思いながら平気に眺めている。浅井君の結婚問題に関する意見は大道易者の如くに容易である。女の未来や生涯の幸福についてはあまり同情を表しておらん。ただ頼まれたから頼まれたなりに事を運べば好いものと心得ている。そうしてそれが尤も法学士的で、法学士的は尤も実際的で、実際的は最良の方法だと心得ている。浅井君は尤も想像力の少ない男で、しかも想像力の少ないのをかつて不足だと思った事のない男である。想像力は理知の活動とは全然別作用で、理知の活動はかえって想像力のために常に阻害せらるるものと信じている。想像力を待って、始めて、全たき人性にもとらざる好処置が、知恵分別の純作用以外に活きてくる場合があろうなどとは法科の教室で、どの先生からも聞いた事がない。従って浅井君は一向知らない。ただ断れば済むと思っている。寂しい小夜子の運命が、夫子の一言でどう変化するだろうかとは浅井君の夢にだも考え得ざる問題である。
(中略)
「理由はですな。博士にならなければならないから、どうも結婚なんぞしておられないと云うんです」
「じゃ博士の称号の方が、小夜より大事だと云うんだね」
「そう云う訳でもないでしょうが、博士になって置かんと将来非常な不利益ですからな」
「よし分かった。理由はそれぎりかい」
「それに確然たる契約のない事だからと云うんです」
「契約とは法律上有効の契約という意味だな。証文のやりとりの事だね」
「証文でもないですが――その代わり長い間御世話になったから、その御礼としては物質的の補助をしたいと云うんです」
(中略)
「……人の娘は玩具(おもちゃ)じゃないぜ。……如何な貧乏人の娘でも活き物だよ。……それから、そう云ってくれ。井上孤堂は法律上の契約よりも徳義上の契約を重んずる人間だって。――月々金を貢いでやる? 貢いでくれと誰が頼んだ。小野の世話をしたのは、泣き付いて来て可愛想だから、好意ずくでした事だ。何だ物質的の補助をするなんて、失礼千万な。……」
(中略)浅井君は面喰らった。
こう怒られ様とは思わなかった。又こう怒られる訳がない。自分の云う事は事理明白である。世間に立って成功するには誰の目にも博士号は大切である。曖昧な約束をやめてくれと云うのもさ程不義理とは受取れない。
(中略)
先生のいう主意は分からんが、先生の様子にはさすがの浅井君も少し心を動かした。
(中略)
漸く気の毒になってくる。
(中略)
表へ出た浅井君はほっと息をつく。今までこんな感じを経験した事はない。
もちろん、これは当時のこの学部がどう見られたかの一つの徴表である。法律家批判は漱石が学んだヨーロッパでは長い伝統を有し、したがってそのクリシェに従った面もむろん有る。しかし明らかに、ここで指摘されている何かの欠落はこの地(この大学?)では一層致命的である、一層悪質である、と映ったのである。幸い作者はまだこれは治癒可能であると見なしているようではあるが。その欠落するものは「想像力」や「徳義」という言葉で言い表されているが、この批判は一般の人々のものの考え方や伝統的な感じ方の反映であると紋切り型で片付けられない。作品の中で対置されているのは、ヨーロッパを含む古典文学に精通した人々(甲野さんに宗近君)で、彼らは十分に「想像力と徳義」を備えると想定されている。そうすると、少々深刻である。何故ならば、特定の法学や法学部にそれに相応しい知的資質が欠けると言われていることになるからである。そうとなれば、同じ批判が今日のわれわれにも妥当するのは自明である。否、一層妥当するだろう。作者が設定した批判する側の人々(甲野さんに宗近君)の存在すら、当時よりも一層、有りえないものであろうから。理知の作用すらも希薄な教室は、無神経や欠落の独壇場であり、これに傷つく者と、これに冒されて自身進むに進めなくなってしまう者、この対極の二つのカテゴリーで溢れる。そして現代では治癒可能かどうかわからない。「今までこんな感じを経験したことはない」という経験をする学生がどれくらい居るだろうか。しかもである。実はこれが法学教育でこそ致命的である。たとえばここで「徳義」と呼ばれているものが如何に法学内部で本来重要なことか。もっとも、このことは誰でも言う。それほどに陳腐である。そしてなお深刻なことに、そのように言う人々自身がまた絵に描いたように「無神経と欠落」を体現している。何故ならば、何が欠落しているのか、どうしたら補えるか、を知らないからである。
むろん、学習相談はこのレヴェルの問題と無関係である。何よりも個人の問題を扱う。その多くはどこに彼や彼女がいても生じた問題であろう。そして解決の処方箋は多くの場合は無く、ただ言葉を介在させることによって、われわれは事柄の決定的な悪化を遷延するための力を貸すだけであろう。
しかし考えてみれば、言葉と遷延は決定的に重要ではないか。想像力と徳義とは何であろうか。浅井君に漱石はどのような言葉を使ったか。「意見は大道易者の如く容易である」(今日の学者に非常に妥当する)。「事を運べば好い」。「断れば済む」。自分を取り戻す作用は一種の留保である。自分が簡単に持って行かれないその分の確保である。その分量は言葉による遷延の分量に匹敵するだろう。そうでなくとも、この遷延が無くなればわれわれには何も残らない。
学習相談室が何にせよ事柄を左右する力を持つとは到底考えられない。一種の無駄かも知れない。しかし、このように問題を先送りする装置は極めて不足している。何しろわれわれ教師は、想像力を教えないどころではない。われわれ自身持っていないのだから。せめてbricolageの対話を学生との間で持つ、という事柄においてさえ、この東大でも、われわれが最低水準に属することは周知の事実である。
(初出、『2006年度学習相談室活動報告書』)
(*)ここで引用されているのは、法学士の浅井が、旧友である小野清三の依頼を受け、小野が恩師・井上孤堂の娘・小夜子との婚約を破棄したがっている旨を伝えるため、井上宅を訪問した場面である。(学習相談室スタッフ注)