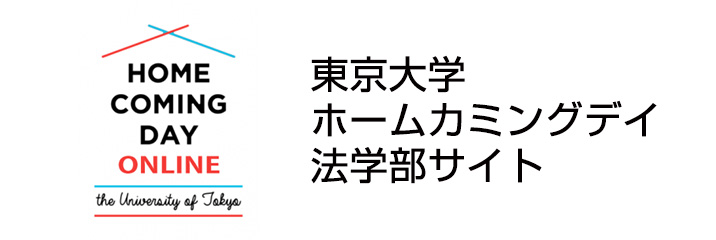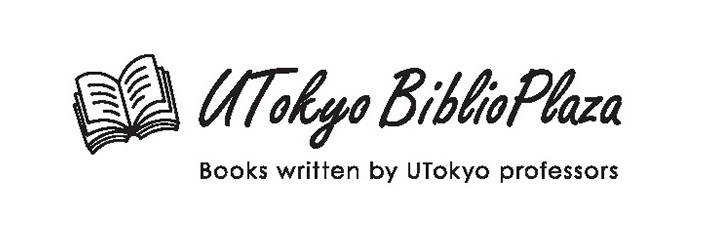コラム60:法学徒の「学問の自由」について
6月4日に開催しました「2020年度 法学部生のための学習セミナー」において講演して頂いた横山高明さんの承諾を得たうえで、講演原稿を全文公開させて頂きます。当日参加できなかった法学部生や法学部進学を考えている駒場生にとっても大いに参考になるのではないかと思います(7.1学習相談室スタッフ記)。
=============================================================
学習セミナー 令和二年六月四日
文学部人文学科哲学専修四年 横山高明
法学徒の「学問の自由」について
文学部人文学科哲学専修四年横山です。よろしくお願いします。私は、文科一類から法学部に進学しました。ただ進学してすぐに体調を悪くしまして、休学して療養していましたが、また回復しないうちに大怪我を負ったりしてですね。それからようやく復学して、二年かけて無事卒業することができました。その後哲学科に学士入学して今に至っております。
それでは、法学部での勉強について、これから述べさせていただくわけですが、今申し上げました通り、私自身は、法学部で勉強して卒業しただけで、研究者でもなければ、司法試験の勉強も一切したことがありません。なので、残念ながら、研究者になるためのアドバイスやら、司法試験合格のためのノウハウについては提供できません。それは他のお二人にお任せすることになります。それで、どうすればお役に立てるかといろいろ考えたんですが、この際メソッドの提案は基本的には諦めます。事前に皆さんからのお困り事を、過去何年か分と合わせていただきました。非常にお困りの方もいらっしゃって、気持ちはよくわかりますし、仮にも「自由」を守る法律家を目指して学ぶ人々が、これほど不自由な思いをしているのは、これはなにかおかしいのではないか、とも思いますから、できれば何か冴えた戦術を提供したいところなのですが、残念ながら力不足で、どうにも自信を以てご紹介できるメソッドを持ち合わせておりません。なので、私としましては謙虚に、私自身の勉強の拙い歩みを振り返ってですね、つまり実際に勉強を進める過程で、思ったことや考えたこと、自分にとって有益だったこと等をですね、一例として紹介することにします。その中で、事前に頂いた質問にも解答していきたいと思います。私の回想にすぎませんから、直ちに役に立つものではないかもしれませんが、特に、どうにも法学部での勉強に展望が開けそうにない方や、今回のコロナ騒ぎで、大切な入門教育が妨げられているだろう、気の毒な駒場の一年生がですね、御自分で工夫される際のなんらか参考になれば幸いです。そういうわけで、参加者の一部の方向けの話になりますので、必要なさそうな方、お疲れの方は、次の酒井先生のお話にそなえて、途中休憩にしていただいてもよろしいかと思います。参考文献は、直接は扱いません。ただ、一応そういうものが話の念頭にはあるというもので、興味があれば後で読んで考えてみてください。
一 理系から文系へ(理系時代)
さっそくですが、質問事項から入ります。「駒場で理系だった人でも法学部の勉強についていけるか?理系から文転した人がついていくには、どのような勉強が必要ですか?」という質問をいただきました。これは私が担当だと思いますし、話の前提としても重要ですので、これに関してまずお話していこうと思います。ちょっと話が長くなるので、とりあえずの結論だけ先に言いますが、元理系の方でも全く何の問題もないです。それから勉強についてですが、仮に法学部のカリキュラムをシンプルにこなす以外何もしなくても、それはそれで大丈夫です。一例をあげれば、私の親友である A 氏が理科二類から法学部に来た人で、とくに予備校等を利用することもなく、(私の見る限り)法学の教科書を愚直に読んで勉強する以外にとくには何もせずに、それでずっと成績もよく、何ら躓くこともなく、ロースクールを卒業して今四大事務所に就職されて大金を稼がれております。彼がなぜ特にプラスアルファの試験勉強をしなかったか、というと、彼は論理学が趣味で本来は論理学の専門に行きたかったそうですが、どうも東大には適切な研究室がなかったようで、手堅い職業を求めて(?)法学部に来ました。ただ論理学の愛好家であることは変わらず、要するに空いた時間は全部論理学研究に投入していたようです。その成果は法と経済学とかゲーム論とかに生かされて、それでローレヴューにも載ったほどですが、少なくとも学部の定期試験とか司法試験とかにそれが直接役立った、必要だった、ということはないようです。それはそれとして、私自身も、元々は理系でしたから、その経験からお話ししますね。
私の最初の大学は早稲田大学の理工学部でした。大久保キャンパスですね。行ったことがある人はいらっしゃるでしょうか。全面狂ったように銀色に塗りつぶされた、複雑怪奇に入り組んで石油化学コンビナートみたいになっている、これぞ理工学部という自負に溢れた、なかなか愉快なキャンパスです。そこで数学や物理学を中心にそれなりに熱心に勉強していました。余談ですが、当時勉強した中には、デカルトの力学や解析、ライプニッツの微積分もあったわけですが、巡り巡って今哲学科に来て、再び彼らと再会することになるとは思いもよりませんでした。単にそれだけでなく、例えば必ず最初に習う微積分のεδ論法などは、哲学において無限を考える際に、就中数学を学問のモデルに想定する哲学者の無限論を理解しようという際には非常に役に立ちました。ここでの教訓は、人生何がどこで役に立つかわからない、ということですね。何事も一生懸命取り組むにこしたことはありません。話を戻しますと、理系の大学に入って古典的理学を学んだものの、その道をやめて東大の文系に入り直すことになりました。これは基本的には勉強とは何の関係もない、個人的な事情によるものでした。ただ、全く学問的な理由が伴っていなかったわけではくて、それが私の勉強の歩みをお話するという本日の文脈では、地味に重要なポイントになるわけです。理系の勉強は、例えば高校で習うものより、より高次元で書かれた数学や物理の方程式を使ってちゃんと高校の時の問題も解けたりして、感心する、そういう意味では普通に面白いものでした。しかし、他方でつまらないな、という面も出てきました。といいますのも、これは一通り勉強してみて初めて気づいたんですが、一生懸命教科書の証明を辿りながら数学なり物理学なり勉強するわけですが、そうして獲得されるものが、隣の友達と寸分違わず同じものにすぎないわけです。お前のマクスウェル方程式ちょっとかっこいいな、とかないですし、あったら困るわけです。自然法則ですからね。そしてこれが私にはちょっと嫌だったわけです。だって、せっかく苦労して勉強してもですね、同じ専門なら誰でも同じものを獲得しているわけですし、そうすると例えばそれで仕事をするとしても、私の代わりはいくらでもいる、ということになりますし、第一私が苦労してやる必要が見出せません。もちろん、アインシュタインじゃないですが、どんどん研究して遂に前人未到の新たな一歩を踏むということは、理屈としてはありうるかもしれませんが、私などはせいぜい学生として優秀くらいのもので、そんな才覚があるとは到底思えませんでしたし。もちろん好みの問題なんですが、これが最大の理由でした。それに加えてですね、具体的な自然法則がどうなっているか、とか、数学の世界の様々な数式がどうなっているか、とか、私の人生に関係ないし正直どうでもいいな、と。それより自分自身が実際に生活する社会の事を知りたいなと思ったわけです。高校までずっと理系でしたし、恐ろしいことに本とか一切読んだことなかったですから、人間の世の中のことを何にも知らないわけです。それでは自分がどう生きていこうか、ろくに考えることもできないわけです。
二 人文学のすすめ(駒場時代)
それで後期試験を利用して文科一類に入学し、打って変わって歴史を感じる伝統的雰囲気の駒場キャンパスに来てですね、いざ本を読み始めてみると、これが非常に面白い。最初に手に取ったのは、国際関係論の授業で紹介された、国際政治関連の本でしたね。ヘドリーブル『国際社会論』とか。とにかく自由にいろいろ考えることができるわけです。理系の勉強の、ある種の厳密さであり窮屈さは全くなくてですね、あらゆる角度から好き勝手に自由自在。先ほどの言い方に倣えば、文系の場合、同じ本を読んで勉強しても、獲得される人文学の学知は十人十色なわけです。その読書から構築された理解はその人ごとに独自のものです。従って、理系と文系では学問の性質が根本的に違うと言ってよいと思います。かたや父なる神が創り賜うた完全なる自然を対象にして、その普遍法則を探求する自然科学であり、かたや人と社会の営みを対象にする人文学。結局、人文学においては、その根底をなす一人一人の人間が全く特殊なる精神存在であって、その特殊なるものが織りなす諸々が学問の対象ですから、そこにはおよそ普遍法則のごとき客観的学知はありえないのだ、と。当時、私はそう思いましたし、今も多少洗練された形でそう考えています。例えば、性質上、というか制度上、概念の客観的意味理解を常に志向している法学であってもですね、民法の体系書並べてみていただければわかりますが、文字通り十人十色です。森田宏樹大先生と潮見佳男大先生の解釈論でさえ、よく見れば全然違いますよね。数学や物理学ではありえないことです。この話と根っこは同じなわけですが、理系と文系では決定的に事情が異なる点が他にもあります。理系の場合、それぞれのディシプリンが論理的に明確に分かれていて、もちろんどの分野でも数式は利用しますし、全ての自然現象は物理学的法則に反することはないわけですし、また互いに技術的な応用はありうるわけですが、しかし各々の専門の「論理」は完全に固有で、いわば一次独立の関係にあるわけです。平たく言えば学問をするのに、技術的な応用の必要以外には他の専門に関心を持つ必要はないわけです。これに対して、人文学はそういうわけにはいきません。互いに混然一体密接不可分といえるでしょう。なんだか当たり前すぎて恐縮ですが、少なくとも右も左も上も下もわからない一年生当時の私にとっては、こういったことも発見でした。例えば歴史学は、当然政治史のみならず、法制史、経済史、技術史、宗教史、芸術史等々いろいろな局面があって、それはそれぞれを専門とする学問の理解によってのみ語りうるところでしょう。法学を一切やらずに法制史を考え語ることはできず、法制史の抜け落ちた歴史叙述は、かなり間の抜けたものにしかならないのではないでしょうか。反対に法学をするにしても、法がまさにそので問われる、我々が生きる政治社会がどのようなものであるかについて知らなければ、何をしてみようもありません。そして人文学の様々な学科はそれぞれ異なった視角から、それぞれに政治社会の姿を明らかにしているわけですから、それらを学ばなければ何ら法についても語りえないと、私は思います。法律学の勉強のみに集中して、それだけで突き進んでいこうとするのは、一見無駄がないように見えますが、喩えていえば、オーケストラの音楽から一個の楽器の音だけ抜き出してそれだけでその音楽を理解しようとするようなもので、かえって効率が悪いというのが私の意見です。法学部の便覧にもこう書いてあります。「法学部紹介の2.教育の理念と授業の構成」のところです。曰く「法学的知恵を身に付け、法律家らしく思考し議論できるようになるためには、まず、基幹的なものから先端的なものまで、広く具体的な法体系を知り、それを支える理論を理解しなければならない。しかし、それだけは優れた法律家となるには十分ではない。現行の法体系の基礎には古代ローマにまで遡る智慧の蓄積がある。一方で日本独特の史的背景もある。それ故、歴史的な理解も必要であ。また、日本法の特質は外国法との比較によって明らかとなる。さらに現代では外国法との接触は日常化している。したがって、比較法的な理解も重要である。さらに、法を基礎づける哲学的・思想的なものへの理解も望ましい。そして、そもそも法と政治・社会との間の連関と相克に全く無知であってはならない。経済学の基本も心得ていることが望ましい。このような観点からして、法学既修者として法科大学院に進学することを希望する学生も、狭い意味での実定法学のみをひたすら学習することは、かえって望ましくない。優れた法律家になるためには、広い堅固な基礎が必要であることを十分に自覚してほしい。主に政治学を学ぼうという学生においても同様である。現代政治の理解に加え、歴史的・比較的・理論的な広がりと深みの中にそれを置き、さらに法学と経済学の基礎を学ぶことが必要である。そうした多角的な学習によって、…云々」と。
そういうわけですから、最初のご質問にあった、理系から文転した人に限らずですね、「一年生のうちからどのようなことを勉強しておくとよいか?」というご質問には、是非法学・政治学以外のいろいろな人文学に、真剣に取り組むことをお勧めします。といいますのは、便覧にはあのように書いてあるわけですが、私の時であれば卒業単位90単位、その内80くらいは法学部の授業で充当しなければならず、他学部の単位が使えるのはわずかに10単位ほどで、なかなか他の学問に取り組む時間的余裕がありません。私などは、これは憲法違反じゃないかと思ったりしました。最近はどうも法律が改正されて10単位ほどノルマが削減されたようですから、少しはやりようがあるかもしれませんが、それでも時間的余裕があまりないことは変わりありません。それから、一応真剣に取り組むことが重要で、そうすることで初めて政治社会を多角的に見るために必要な、独立の視角として機能する一個の眼が確保されると思います。時間は短くてもいいですから、その学科の専門に進む学生と同じ気持ちで本気で考えることが重要です。ちょっと試しに聞きてみるというスタンスでは、多少の知識は得られても、特有の視点は獲得できないと思います。私の具体的経験としては、一年生のときに基礎倫理学という授業がありました。そこで黒田亘『行為と規範』という本を課題図書でだされ、それはそれは真剣に取り組みました。黒田さんというのは、昔の東大の文学部哲学科の先生です。実に面白いし、我ながらすごいレポートが書けたとか思いましたけど、当時は、これはジャンルとしては何をやっているのかもわかりませんでした。ただ後から振り返ると、あの時一生懸命やったおかげで、哲学というものへの橋頭保が確保されたと思いますし、自分がそれから法学をやる際にも有形無形に役立ちました。有形に、というのは、例えば刑法第一部の勉強で、山口厚先生の『刑法総論』の故意に関するところで、議論が依拠していた高山佳奈子先生『故意と違法性の意識』を読んでいると、その中に先ほどの黒田亘『行為と規範』がでてきました。ですから高山先生の議論、ひいては山口先生の議論を理解する際に具体的に役立った、というわけです。実定法の議論も、よく読んでその議論が依拠するものを辿っていくと、まともな議論であれば、歴史学や社会学はもちろん、哲学の本にも物理的に道が通じているものです。そういう深みのある人文学的なテキストだからこそ、さらに勉強したり、仕事をする際に、繰り返し立ち返り、問答できる善き友人となるわけです。この点に、いわゆる予備校の教材の類は致命的な欠陥があります。無形に、というのは、無形の話ですから手短な説明は困難ですが、法学の勉強をするにも、例えば教科書に書かれたドグマーティクを理解しよう悪戦苦闘する際にも、常に哲学の勉強で獲得された視点が働いて生かされるということです。そういうわけで、諸々の人文学をお勧めしているわけですが、中でも差し当たり一番簡単に手堅く取り組めるのは、歴史学だろうと思います。法学部で学ぶ実定法も、元々ヨーロッパ政治社会の中に生成したヨーロッパ近代法を明治時代に輸入してきたものですから、実定法の勉強においても、ヨーロッパというものを知ることは非常に重要なことだと私は思います。そのためにはまずは西洋史を学ばないと話になりません。私は元理系で世界史もほとんど知りませんでしたから、駒場では最初は歴史の授業は避けていたのですが、必要に気づいてから、夏休みを利用して山川の『世界歴史大系』ドイツ史フランス史イギリス史を読んで最低限の歴史的イメージをつかみました。時間はかかりましたし、いきなり通史だけ一気読みするのが適切かはわかりませんが、歴史叙述ですから、少なくともわけが分からなくて読み進められないということはありません。「法学部では分野横断的な内容をどれだけ扱うのか?」というご質問がありました。ご質問の意図に応えていないかもしれないのですが、法制史は当然として、外国法や憲法の授業では、歴史学自体が講義の内容、議論の一部を成すと言っていいと思います。私も、もし世界史を勉強していなかったら、少なくとも履修や勉強の仕方は全く違ったものになったかもしれません。
さて、ここまで駒場時代までを振り返ってみる中で、ありきたりな人文学の勧めを、多少の実体験を添えて述べてきたわけですが、最初の A 君の話と食い違うじゃないか、と言われてしまいそうです。そりゃ何事も勉強するに越したことはないけど、本当に法学部での勉強に必要不可欠なのか?と。これに対する答えもですね、差し当たっては凡庸の極致で申し訳ないのですが、これは人による、ということになるかと思います。それはなぜなのかと、それは後で再度触れるとして、一応このことに関連する話として、次の項目に移ります。
三 問い→方法→対象 と 読書の仕方
ここで唯一メソッドらしき話をさせていただこうかと思います。とはいっても、また当然すぎて価値がないかもしれませんが、これも私自身は、途中で気づいた話です。学問上の方法論に関して、しばしば方法と対象の関係についていろいろ言われたりします。法学部でも、というかむしろ法学部でこそ盛んに、「方法が対象を規定する」とか「法学のメガネが」とかですね、なんだか一見実にもっともらしい、だけど、ちょっと考えるとずいぶんと怪しげな話があります。もちろん方法や対象についてよく吟味することは非常に大切なんですが、それはそれとしてですね、今私がここで言いたいのは、それよりもまず先に、「問い」というものがあって、「問い」がいったいなんであるのか、ここを押さえることが決定的に重要であると、そういうことです。「問い」が明確になれば、仕事の中核は終わっているといっても過言ではありません。今説明の便宜のために、あえて適当な図式を例示しますと、例えば今英文科の学生が卒論を書くにあたって、「『ロビンソンクルーソー』と『ガリバー旅行記』を比較する」とします。そうすると対象(=著作)と方法(=比較)は一応決まっているような気もするわけですが、この「対象と方法」で取り組むことのできる「問い」はいろいろとありうるわけです。この比較によって解明したいのは、両著作の作風・技法の違いなのか、ダニエル・デフォーとジョナサン・スウィフトの人となりの違いなのか、17・18世紀のイングランドとアイルランドの関係や違いなのか、ピューリタンとアングリカンの宗派の違いなのか等々、いろいろな「問い」がありえて、「問い」が何か未だ定まっていないわけです。逆に言えば、自分にとっての「問い」は一体何であるのか?これが探求されるべき第一の目標であるといえます。一つの「問い」が定まれば、その解明に役立つ「方法と対象」はいろいろ考えられますし、また複数の「方法と対象」から得られた分析結果を、一つに取り纏めて総合することができるのも、その固有の「問い」だけです。なので「問い」が非常に大切なわけです。それでですね、例えば卒論を書くとかいう場面では、もちろん最初から「問い」が明確であればベストですが、普通は大雑把な「問い」から出発し、調査作業していくうちに、だんだんとその「問い」が精密になっていって、その輪郭が確定したころには仕事はだいたい終わっている、という感じだと思います。ただそのためには、「問い」はなんであるかを常に探求する姿勢がないと、いつまでも明確化されずに、研究もまとまりなく迷走することになります。「問い」が不明のままに、「答え」がでてくることはありえないわけですし、「答え」は、必ずある「問い」との関係においてのみ意味を持つわけです。理系だと問いと方法は区別が困難ですが、人文学の学問というのは、必ずなんらかの個別の「問い」を起点にした、あえていえばですが、[問い→〈方法〉→対象]の三項から成っているといえると思います。二項ではなくてね。この点は、当然法学も例外ではありませんし、むしろ実際の裁判で、先ず争点を整理・決定し、その争点=問いを基軸に審議を展開するあのプラクティスは、いかに「問い」を押さえることが要であるか、をなによりも雄弁に物語っていると思います。本人訴訟ですが、裁判をした経験からしますと、争点というのは、現実の紛争の当事者双方の勝手な言い分の鬩ぎあいから析出してくるものですから、「生きた係争事件についてではない、構成要件的に分解された架空的法律ケース」である試験の事例問題では、争点それ自体も、その意義も見えづらく、それゆえに答案もどうにもジャストミートした感じにならないという問題があるかと思いますが、有効性の程はわかりませんが、裁判になったつもりで答案を考えるのではなく、当事者甲になったり、乙になったりしながら、裁判に負けないように言い分を捻りだすような努力をすると、争点を生成しやすい、かもしれません。
話を戻しますと、幸か不幸か法学部には卒論がないわけですが、しかしこの話は、研究以前にまずもって普通に勉強をしていく際に常に重要です。つまり、我々が勉強する際には、授業を聴いたり、本や論文を読んで勉強するわけですが、その際にですね、論者がいったい何を問うているのか、これを先ず押さえることがその議論を理解するために必要不可欠な、いわば鍵です。まあ、そんなことは高校生で習ったよ、という方には本当に恐縮なんですが、私のような察しの悪いタイプの人も中にはいると思うんですよね。ですから以上の話を基に、読書の仕方、読書の方法論を述べますと、第一に、著者が何を問うているのか、議論の全体を支える問いは何か、部分的な問いは何か、これらを確実に押さえて、差し当たりその問いを共有することで、それらを起点として紡がれている著者の思考を丁寧に理解するように読むことです。著者の問いが何か判明していないならば、それは全く読めていないということです。と同時に、第二にですね、自らの問題関心、自らの問いを以て本を読むということです。そういう主体性が必要だと思います。いわば、自らの問いを懐中電灯にして、それを光源にして照らしながら、目の前に構築されている著者の思考を辿っていくようなものです。これはどういうことかというと、先に経験的な話をしますと、何年か勉強を進めてくると、本棚に読み終わった本が増えていきます。が、残念ながら内容を必ずしも覚えておりません。結局後に残るのは、自らの問題関心に関連して、それに位置づけられた、つまりは自分自身のささやかな人文学の、その中に位置付けられた内容だけです。お分かりかとは思いますが、要するに、人文学の本を読むというのは、著者と自分との対話なわけです。数学や物理学の教本を読むような受動的な情報伝達の関係とは本質的に異なります。最初に言及しましたように、著者と自分ではそもそも人文学的な様々な物事についての理解が不可避的に異なります。問題関心も異なります。だからこそ読書の仕方としては、まずは問いを起点に、いちいち著者の思考を正確に辿る大変な努力というものが必要であり、それによって著者と自分の理解や問題関心の差異が明らかになり、同時に、曖昧だった自分のほうの理解や問いも形をとって析出してくる。そういう仕方で、書き手と読み手の固有の対話が鮮明に像を結ぶわけです。その固有の対話から、我々は著者自身の思考内容を越えた独自のものを見出していくことにもなりますから、従って、理系におけるとは異なって、読書を積み重ねて、各人の人文学というものは、ますますもって十人十色になるわけです。
四 外国語文献精読ゼミ(法学部時代)
そういうわけで、言葉で書かれた議論を正確に読む、ということが先ず決定的に重要であり、その技能は、あらゆる場面で汎用的に威力を発揮する、したがって唯一誰にとっても有用な、いわば人文学におけるマスターキーなわけです。ところが、客観的な情報と数式で記述された理系の論述とは違って、人文学のテキストを正確に読む、というのは実は容易なことではありません。この技能をトレーニングしてくれるのが、法学部の外国語文献購読のゼミです。外国語の翻訳はそれ自体既に哲学だ、などと言われますが、精密な翻訳作業は、言葉と意味というものをまるごと深く反省する機会を与えてくれます。そして限りなく精密に読解できる先生が、その水準で逐一細かくチェックしてくれるからこそ、不正確な読解に甘んじることのない、精密読解のトレーニングが可能になります。ところが、端的に言って、そのような精密な読解能力がある方は、世の中にあまりいません。なので、ここでのトレーニングは他所では得難い非常に貴重なものです。実際の作業は文法事項や辞書の使い方からはじまって、なんだか地味だな、とか、独文仏文の学生みたいだな、と思われるかもしれませんが、法学政治学の文献を読解するには、当然その学問的理解がなければ読めませんので、単なる語学学習ではありません。また、同じテキストを参加者が共有して一学期間読み進めていきますから、そこには思考の並列化といいますか、時間をかけて用意された共通了解というものがありますから、その状態を前提として初めて可能な、教室の一方的講義では伝達が難しい、高度な内容の教授というものがあると思います。
また、外国語の文献を読めるということ自体も、非常に重要です。人文学のほとんどすべては、ギリシャ・ローマに遡る欧米の学問の伝統と蓄積の上に生成しています。学問上のあらゆる概念が輸入品です。最末端に位置する、日本人の学者が日本語で書いた議論だけ読んで勉強しても、よくてバロックな感じにしかなりません。しかし、古典であれ現代のものであれ、翻訳された本というのも、もちろん有用性はあるのですが、やはり内容理解となるといかに優れた翻訳でも一定の限界があります。元の言語で読んだときと、日本語訳を読んだときでは、再び音楽に喩えていえば、生のオーケストラの演奏と、再現されたゲーム機の電子音くらいに、鮮明さに差が感じられます。なので、やはり一つでもいいので、ヨーロッパ言語をトレーニングして、その生の思考に触れられるようになる必要があると思います。そういうわけで、是非外国語文献購読のゼミへの参加をお勧めします。そのためにも、駒場の学生には、ヨーロッパ言語の学習を最優先にしてほしいと思います。正確な読解能力や、外国語読解能力は、例えば実際の裁判などで、様々なテキストを調査し、主張立証に利用する際にも、絶大な威力を発揮します。調べればわかる法律の知識などよりも、はるかに力量の差が出ます。
五 まとめ
従って、二の最後で、法学部での勉強に何が必要かは人による、と言わざるを得なかったのは、そもそも人によって問題関心や物の見方が異なり、またそれによって、同じく法学部で法学政治学の勉強をするとしても、各人が勉強を進めていくために、何が必要となるか、どのような理解を獲得するか、どのような学習の航路をとるか、そういったことも大きく左右するからだと思います。一で紹介したように、私とA 氏では問題関心もモノの見方も見事なまでに対極的だったわけです。私は政治社会の事を知りたいな、画一的な勉強は嫌だなっていう問題関心でしたし、A 氏は A 氏で論理学マニアで、(私の見るところ)形式をこよなく愛する極端なタイプの人でしたから。実際にですね、本当に面白いのですが、二人で勉強会その他で、実定法科目を中心にいろいろな論点を議論したのですが、毎度のように根本的なものの考え方の違いに、議論は帰着し、還元されました。民法の解釈論の細部まで、その影響は及ぶんですね。なので、長々話しておいて、結論まで陳腐で申し訳ないのですが、自分の問題関心を大切にして、そこから主体的な勉強、というのはつまり、自分の中で有機的体系的にしっかり位置付けるような仕方で一つ一つを理解していく、そういう勉強を心掛けることが重要かと思います。そこから自ずと自分が何をどう勉強すべきかも見えてくると思います。答案の類も、型に嵌らず自分の思考回路に沿って好きに書いたらいいと思います。筋が通っていれば、これで案外通用します。文学部と比較してみますと、文学部の学生は、そもそも自分の勉強したい学科に進学して、そこで自分のやりやすい、やりたい研究をするだけですから、法学部に特有のある種の困難とは基本的に無縁です。ですが、法学も人文学ですから、本質的には変わらないはずです。どのようなスタイルでもいいですから、主体性を失わないように取り組むことが、「自由」を奪われないために必要なことだと思います。結局のところ、そもそも自分の、自分だけの人文学がありうるだけなわけです。にもかかわらず、自分なりの意味理解の蓄積ではなく、逆に、あたかも形式的な情報のインプットというような勉強スタイルになってしまうと、相当無理をすることになりますし、仮に試験はクリアできても、長期的にはまずいと思います。その先、法学政治学を用いた仕事をする、となると、自ら問題を発見し、自らそれに対して思考し、自ら解を生み出していかなければならないわけですから、そこではなんにでも対応していけるような、自前の人文学が育ってないと困るわけです。それというのは、主体的な勉強の中で、あーでもない、こーでもない、こっちを調べてみようか、あっちを確認してみようか、という悪戦苦闘によってのみ形成されるものだと思います。その試行錯誤の途中で、没になったものも含めてですね、沈殿してストックされた様々な思考回路やアイディアが、新たな問題に取り組む際にまた生きてくるわけです。つまり、勉強における「分からない」は全く無駄なことではありません。「わかりやすい」ものは、その筋トレの機会を失ってしまう意味でまずいだけでなく、そもそも、学者が何百頁、何千頁かけて書いた学知は、別に冗長に書かれているわけではないので、それを理解するには、それだけの分量をそのまま読むのが最も近道なのであって、短く要約された教科書的記述では、その思考を理解することは不可能です。つまり、「分かりやすい」という話は二重三重に問題があります。
参考文献に挙げた上山先生の本は、「分かりやすく」歪んだ法学教育について、まさに人文学的に考察し、その顛末についてもいろいろ書かれています。上山先生はそうは言っていませんが、私の見るところでは、これは一言で言えば、「批判精神」が抜け落ちる、ということに尽きるかと思います。なかなか愉快な本ですので、是非読んでみてください。「今日の日本の法学教育においても」と警鐘を鳴らしておられるわけですが、実に43年前というのが笑えます。43年といえば、22歳で卒業した学生が65歳で定年退官する年月です。霞が関も、上から下までそんな感じというわけです。そりゃ賭けマージャンもすれば、貧困調査にも出かけようというものです。学生の皆さんに置かれましては、そのような残念なものに成り果てることのないよう、つまり「自由」を喪失して悪の片棒を担ぐようなことにならないよう、自由と正義を貫けるよう、是非「批判精神」というものを養ってほしいと思います。その際、「批判精神とは、対象と鋭く距離をとって云々」とかスローガンだけ覚えても何の意味もありません。「批判精神」とは、いったいどういうことであるか、深く考察し、自分なりの理解をつかんでほしいと思います。以上です。
参考文献
〇F・ヴィアッカー『近世私法史』(鈴木禄弥訳, 1961年)原著《Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtingung der deutschen Entwicklung, Göttingen 1952》
「裁判官が学説に拘束されていることに照応するのは、法律家のための新しい学問的教育理想であった。どの実証的法文化もそうだが、パンデクテン法学にも、専門的法教育の一定のプログラムが結びついていた。しかも、そのプログラムたるや、内面的および外面的な司法の危機および法律家の危機がその後にいろいろと生じたにもかかわらず、今日まで引続き行われているのである。すなわち、若い法律家は、大学Hochschule に入るやいなや、歴史についての諸講義による準備を受けた上で、体系的な順番で、かつ、概念的に厳格に整序された形で、教材を受けとる。それから、かれは、法の適用を試みているのだが、それは生きた係争事件についてではなく、また、訴状記録についてですらなしに、構成要件的に分解された架空的法律ケースについてである。この法律ケースを法的な請求権のもとに正しく包摂すること(訴権とはなにか qualis sit actio?)が、かれのもっぱらの課題である。同じ諸目的が、第一次法律家国家試験の仕組を規制している。[法律家]育成のかかる理想は、往々にして攻撃され、往々にして戯画化され、かつもちろんおそろしく一面的なものであるとはいえ、この理想は、そのはじめにおいては、道義的かつ国民政治的な一の背景をもっていた。その背景というのは、フンボルト的教養主義の精神より発するドイツの大学の革新と国僕 Staatsdiener という道義的理想とであった。前者の象徴は、一八一〇年のベルリーン大学の創設であり、また国僕というのは、人文主義的かつ学問的に育成され、かつカントの義務論を信奉するところの者であった。この意味において、サヴィニーは、その著《使命》において、国家のための法律家の教養について、記述した。すなわち、サヴィニーによれば、国民的法文化のために法律家は法源に精通しかつ純粋の理論を駆使すべきである、というのである。…(略)…人文主義的教養理想の終焉によって、アカデミックな法律家は、社会的かつ精神的な危機のうちに、落ち込んでしまっている。この危機の全貌もまた、以上のごとく解することによってしか、これを明らかにしえない。」(519頁~521頁)
〇上山安敏『憲法社会史』(1977年)
「(2)このように、法学教育が国家試験への依存を高めたことによって、法学教育は学問の自由との矛盾という苦悩の十字架を背負いこんだ。その最も集約的にあらわれた矛盾の形態は、ドイツに特有な補習教師の制度である。これは、大学町に定住する大学非公認の国家試験用の私塾である。法律試験は学生をして、一定数の定式を復習することになれさせ、法の原理を把握しえないで短期間に知識を集中する暗記的理解に陥らせた。これが補習教師をつくったことは、一八四八年の制度改正で国家試験が法律学の試験になってからこの制度があらわれたことからも明らかであろう。しかも法律学的な国家試験がステロタイプ化すると同時に受験私塾を繁昌させ、これの救けなくては今後はほとんど試験を及第することは不可能となったのである。…(略)…なぜこのような大学の教育体制を掘り崩してしまうような私塾ができたのかは、大学における教育と研究に問題があった。そこには実務と学問との間に距離があった。大学は国家試験のための予備校化の動きを見せたが、また歴史法学以来の伝統を保ち、アカデミッシュ・フライハイトの建前を崩さなかった。したがって、それは歴史と哲学と古典のアカデミッシュな馥郁たる学問の香をもち続けた。だが試験の実態を知り、実学としての法律学に附着している歴史と哲学と古典の虚学なることを嗅ぎとった学生は、研究と直結した講義を素通りして試験と直結する途を、私塾というルート――これこそあらゆる学者が学問の品位に欠けたものとして罵倒したものである――を、利用したのである。補習教師制は、教わる側の座席(Schulbank)と教える側のアカデミッシュ・フライハイトとの間の谷間に乱れ咲いた隠花植物であった。」(172頁)
「今日の日本の法学教育に視座をおいても、大学の法学教育が司法試験のための予備校化の危機を深めつつあり、大学教育の在り方の根底的姿勢が問われている現況において、ドイツの法学教育が、国家権力をバックにした国家試験とさらにそれに寄生した補習教師という私塾との圧力の前に、学生の要望に応えて教育方法自体を移動修正していったという苦悩の歴史は、われわれにとっても切実な教訓を与えている。」(158頁)
Q&A 話の流れの中で、拾いきれなかったご質問に、コメントします。
Q.司法試験や公務員試験を受けない人は単位取得で不利になりやすいですか?
A.不利になるということは、全くありません。むしろ、人によってはですが、資格試験勉強が足を引っ張る可能性もあると思います。なぜなら、大学の授業や定期試験が問うところと、資格試験が要求するものは、ベクトルが違うからです。だからこそ、後者に最適化している司法試験予備校は、こと試験の短期合格という目的に関する限りは、「分かりやすく」効率的で、有効性があるわけです。そうでなければ、まるっきり詐欺です。もちろん、資格試験勉強の成果を定期試験にも流用できる部分があることは間違いないでしょうが、時間は有限ですから、資格試験勉強をしている分だけ、それとは方向性の異なる大学の勉強のために使える時間は減ります。しかし、当然後者の学習も定期試験のために必要でありますし、中には実定法科目であっても後者の学習なしには不可必至の試験をなされる素敵な先生もおられます。(遺憾なことに)資格試験とは無縁の、基礎法科目にいたっては、言うまでもありません。
Q.学問分野が絞り込めず、もっと学問がしたかったが、将来が不安で就活している。体調が悪く困っている。就職と勉学で迷ったりしなかったのか?
A.まず、私自身は、およそ就活や仕事ができる状況ではなかったので、そういった件で迷うことはありませんでした。ただ、もともと学びたいという気持ちを持って東大に来たので、体調不良に見舞われなくとも、迷うことはなかったと思います。私ならむしろ、このまま無学で歩んでいって将来困りはしないか、の方に不安を感じたことでしょう。
次に、直面する困難というものは、人それぞれですから、それに対して横から、こうしたらいい、ああしたらいい、ということは言えたものではありません。ただ、自己啓発セミナーみたいで恐縮ですが、我が身に降りかかった幸運も災厄も、(法的社会的責任等は別として、)出来事それ自体は他の人に代わってもらうことは不可能なので、結局自らが引き受けるしかない、という事情がありますので、予めその運命的構造を前提とした、自分の人生に責任をもった生き方をしたほうがいいんじゃないでしょうか。
第三に、学問をする、ということについては、第一に、私の考えでは、学問分野を絞り込む、ということは必要なこととは思いません。もちろん、研究者として大学でポストを得る、ということになると、これは専門家稼業ですから、担当分野について徹底的に知悉することが仕事上要求されそうですから、それがいかなる分野であれ、そのためには大変な勉強量が必要になりますので、普通の人間であれば、取り組む「分野を絞り込む」ことが避けがたい、のかもしれませんが、しかしそもそも、「学問をする」ことと、「研究職に就く」ということは別のことだと、私は思います。従って第二に、単純に学問をしたい、ということでしたら、自分なりの学問の仕方さえ身に付けられたなら、就職された後も、自由に学問を続けたらよいのではないでしょうか。大学というのは学問の仕方を学ぶところだと思うので、それが本来期待されているところだと思います。そうではなく、大学の研究者になりたい、ということになりますと、これは私には答える能力がありません。就職難だと聞いています。
最後に、体調不良については、私がお勧めできる一つの選択肢としては、一切の仕事を完全に止めて、回復に専念することです。具合が悪い状態では、いくら作業しても成果は貧しいものにならざるをえません。逆に、休養して心身のコンディションを回復することは、復帰後のパフォーマンスを上げ、また普段狭まりやすい視野を広げる意味でも、決して足踏みではなく、これも立派な前進だと思います。