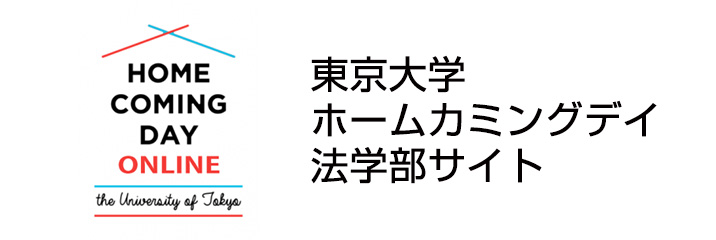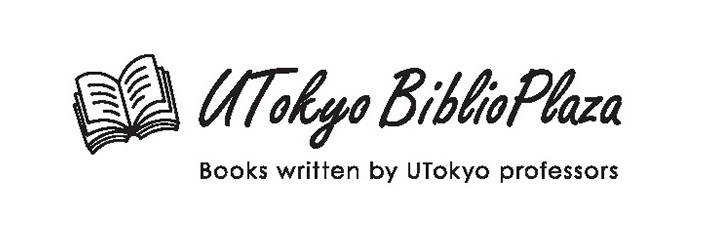栗原彬編『証言 水俣病』によると、杉本栄子は3歳のときから網元をしていた父親から漁師としての英才教育を受け、小学校4年のころには網元の跡取りとして漁を取り仕切り、30人の網子から「親方」と呼ばれるまでになっていた。水俣市茂道地区の村民たちは、海の幸がたくさん獲れれば皆で分け合い、畑の人手が足りないときは無報酬で手伝うなど、みんなが家族のように助け合う仲の良い村だったという。ところが、栄子の母親が茂道で初めて水俣病を発症すると、村人の態度は一変し、栄子一家は激しいいじめと差別に遭うことになる。
当時は水俣病の原因も特定されておらず、奇病、伝染病などと言われ、「うつる」と思われていたこともあり、村人が栄子の家の前を通るときは口を押えて走り抜け、栄子一家は村道を通ることも許されず(村道に通じる家の前に大量の糞尿が置かれていたこともあった)、隔離病棟に入れられた母親を見舞うために、藪の草を鎌で払いながら通うような日々だった。「困ったときはいつでも来(け)え」と言ってくれていた近所に住む親戚までが、「親戚の恥さらしが!」と怒鳴りつけ、「二度と来んな!」と罵声を浴びせる始末であった(藤崎童士『のさり』)。
ある日母親が一時的に退院してきたとき、母親が隣のおじさんに崖から突き落とされるという事件まで起きた。「わっどま(お前たち)歩ぶな。部落の道ば歩べば困っどが」というおじさんに、カッとした栄子が仕返しに行こうとすると、父親は「仕方がなかがね。どうせ死ぬとなら、人ばいじめて死ぬよりもいじめられて死んだほうがよかがね」、「人様は変えならんとやっで、自分が変わっていけばよかがね」と言って、仕返しすることを許さなかった。父親は日ごろから、「網の親方は、人を好きにならんば一人前にはならんとぞ。人様のおかげち思って魚は捕らんばんと」と栄子に語り聞かせていたが、村人たちを本当に信じられないようになったとき、栄子は「父は嘘ばいったっじゃなかろうか」と思い悩むようになる。
しかし、いやがらせをした人たちも、次々に劇症の水俣病を発症し、病気を隠すために病院にも行かず、多くの人が亡くなった。栄子たちが裁判を始めると、水俣市はチッソのおかげで成り立ってると思っている村人たちから「原告は金の亡者だ」などと言われ、新たないじめが始まったが、後に勝訴判決が出ると、村人たちも「ようやってきたね」と言って、少しずつ変わっていったという。「えい子食堂」を始めると、店に来た昔なじみの人たちが、少しだけ飲んで、「栄ちゃん、こらえんな。今までのことこらえてくれ」といって、土下座して謝ってくれたという。
母親の発病後しばらくして発病した父親も1969年、水俣病で亡くなるが、亡くなる前に、「水俣病も“のさり”じゃねって思おい」と言い残して亡くなった。水俣では、運よく大漁に恵まれれば「のさった」と言い、不漁のときには「のさらんかった」という。つまり人間の意思や行為とは無関係に訪れる天の恵みを「のさり」というのである。
一時は父親の言葉を真剣に疑った栄子であったが、長い年月ののち、「本当に病気のおかげだなって」思うようになったという。なぜなら、母親が人様より早く病気にかかったためにいじめられたが、そうでなければいじめる側に立たされていたはずだ、と思い、人として育ててくれた父と母、網の親方として育ててくれた村の人たちに感謝の気持ちを持てるようになったという。
普通の人間ではなかなか到達できない境地だと思うが、類のないほど悲惨な病気と、すさまじいいじめと差別という極限的な苦しみを潜り抜けるなかで、「人様は変えならんとやっで、自分が変わっていけばよかがね」、「水俣病も“のさり”と思え」という父親の教えが大きな支えとなり、徐々に自らの実感ともなっていったのかもしれない。(敬称は略させて頂きました。)(文責 稲田)