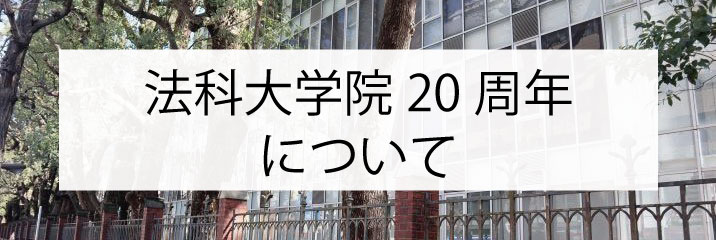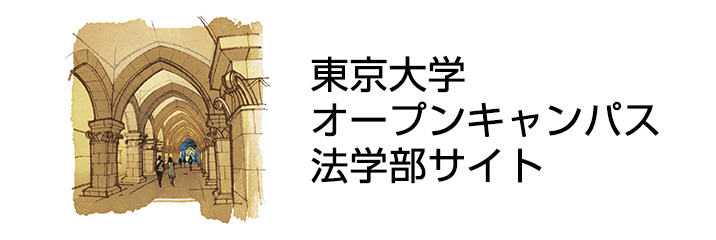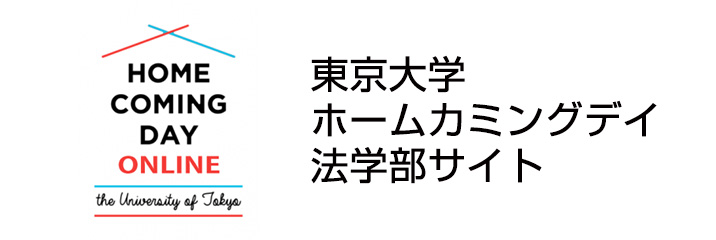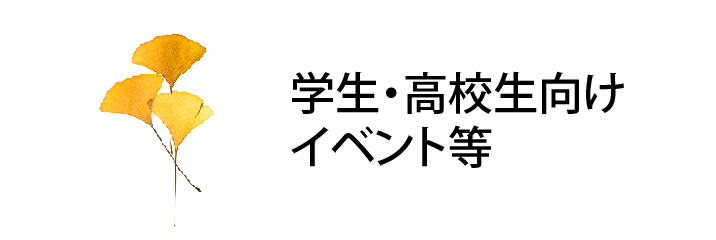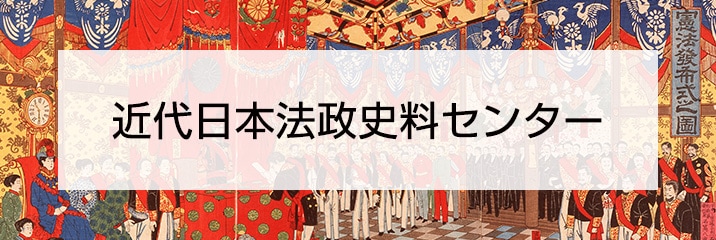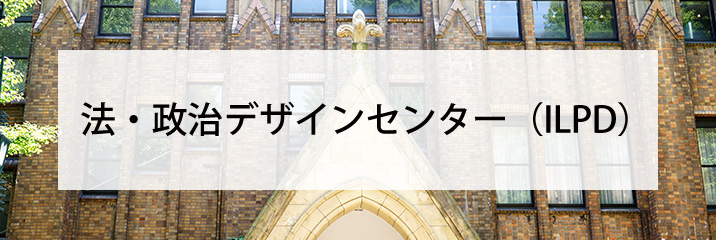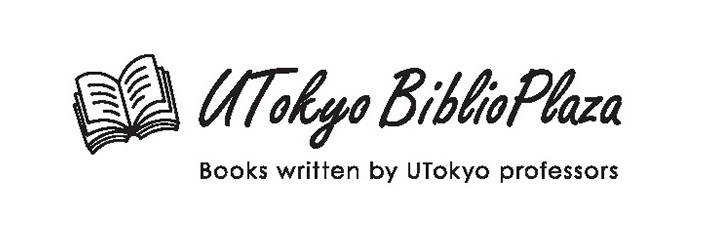研究科長・学部長挨拶

2025年7月24日より東京大学大学院法学政治学研究科長および東京大学法学部長をつとめています、橋爪隆(はしづめたかし)です。専門は刑法です。
私からは、「東京大学法学部で学ぶ」ということ、また、その学びを提供する「東京大学法学部」、「東京大学大学院法学政治学研究科」の特徴をお話ししたいと思います(以下では、適宜、東京大学法学部を本学部、東京大学大学院法学政治学研究科を本研究科といいます)。
東京大学法学部は、司法省法学校(1872年(明治5年))、開成学校法学科(1873年(明治6年))を前身とし、1877年(明治10年)の東京大学の創設とともに設置され、東京大学とともに2年後には150周年を迎えます(法学部の歴史はこちら、年譜はこちら)。
本研究科・本学部は、由緒ある法学・政治学分野の研究・教育の拠点として、一方で、日本における研究において、多くの優れた法学・政治学の研究者を輩出し、最高水準の研究を集積し、学界を牽引する役割を担ってきました。また、他方において、毀誉褒貶ありつつも、国家や社会の屋台骨を担う人材を育成し、輩出してきました。
法学部の卒業生の進路といえば、何よりも、官僚、裁判官・検察官・弁護士、ジャーナリストというイメージを持たれる方も多いのではないかと思います。これらの人材を本学部が輩出してきたことは確かですが、本学部の卒業生は、いわゆる民間企業やビジネスの分野で就職し活動する人も多く、数としては多数を占めます。このことは、本学部が、法学と政治学の素養を身に付けた人材を社会のさまざまな場に送る役割を担ってきたことを示しています。
「法学と政治学の素養」と言いましたように、本学部での学びの軸となるのが、法学と政治学です。例えば、政治学は経済学と同一学部であるなど大学によって様々な専門の編成がありえます。その中にあって、この法学と政治学とを両輪としている点が、まさに本学部そして本研究科の特徴の一つであり、その「強み」の一つです。
法学・政治学は、社会を扱う社会科学の一つであり、異なる価値観・観点・立場・バックグラウンドを持つ多様な人が存在する社会において、その課題や紛争をどう解決するのか、「規範」に着目するのが法学であり、政策や意思の決定過程の「現象」に着目するのが政治学です。法学および政治学は、長い歴史と膨大な議論の蓄積のもとに、「人間の社会で生じる様々な問題がどのように解決されているのか、解決されるべきか」を探究し、社会を成立させ、社会における問題を解決している規範や考え方、社会事象を分析するための思考枠組を探究するものです。例えば、AI等の科学技術の進展についても、新しい技術を社会でどう受け止めるのか、その技術の展開のためにどのような制度面の手当てをすべきなのか、技術の進展自体にどう社会の要請や考慮を埋め込むべきなのか。これらは、法学および政治学が担うものです。技術の進展も企業の活動も社会の存在を抜きにしては語れません。新たな事象が生じるほど、法学と政治学の重要性は重みを増していきます。社会における問題や課題を発見し、認識し、理解し、その解決のための方法を議論し、社会の制度をデザインしていく、そのために不可欠の思考枠組だからです。そしてまた、そのような性格ゆえに、法学・政治学には、歴史や諸外国の状況、国際的な分析・考察が当然に含まれますし、また、経済学、社会学、哲学等々の他の様々な分野の学びが必要になります。
もう一つの「両輪」が、研究と教育です。本研究科・本学部においては、第一線で活躍する研究者が、同様に、教育に心血を注いでいます。本研究科・本学部の教育は、教員個人の最先端の研究に裏打ちされたものであり、後進の育成として重要な意義を有するものです。他方で、教育における刺激や示唆は研究へと結びつき、両者は、研究科・学部という組織としても、個々の教員というレベルでも、「両輪」として機能しているのです。
法学・政治学の研究と教育を担うのが、本研究科が誇る教授陣です。法学・政治学のさまざまな分野において、約80名の教授・准教授が、日々研究に取り組み、その成果を教育へと活かしています。教員の規模の大きさは、研究領域の多様性へとつながり、研究科全体として、法学・政治学の専門分野を幅広くカバーしています。東京大学出身者に限らず、また、国籍や性別を問わず、多様な人材を擁しつつあります。
法学・政治学の研究と教育を支え、それ自体が「知の集積」であるのが、図書・資料です。法学・政治学の専門図書館として、国内最大規模の蔵書数を誇る法学部研究室図書室を備えていること、また、明治期に日本で刊行された新聞雑誌の国内最大のコレクションを含め、近現代の新聞・雑誌資料や貴重な一次資料を収集・保存し、研究に供する近代日本法政史料センターを有することは、研究・教育の拠点として誇りとするところでもあります。
さらに特筆すべきが、「知の共同体(コミュニティ)」としての歴史と伝統です。法学・政治学における学問の不断の蓄積と継承を中核とした、東京大学法学部・法学政治学研究科の「コミュニティ」は、その教員、職員、学生、卒業生など、本研究科・本学部に関わる全ての人によって、成り立っています。
激動の環境下にあって、このような本研究科・本学部の持つ強みを継承し、次の世代につないでいくこと、そして、多少なりともその強化を図っていくことが、私の法学政治学研究科長・法学部長としての職責だと考えています。
東京大学法学部で学ぶことに関心を寄せてくださっているみなさんは是非こちらのページもご覧になってください。法科大学院への進入学をお考えの方はこちらを、修士課程・博士課程での研究をお考えの方はこちらを、そして、ご支援をお考えくださっている方は、こちらを、併せてご覧いただければ幸いです。
改めまして、本学部・本研究科のウェブサイトをご訪問いただき、ありがとうございます。
東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長
橋爪 隆