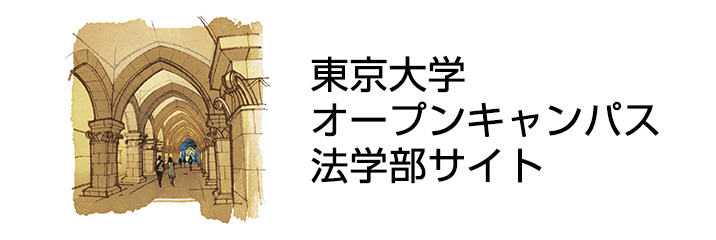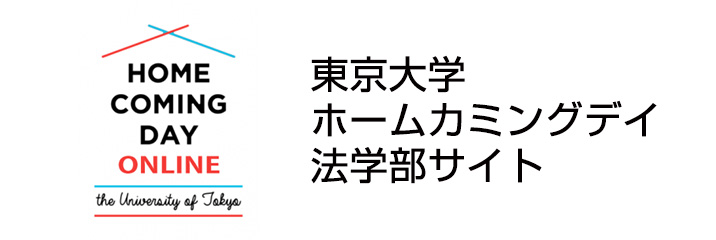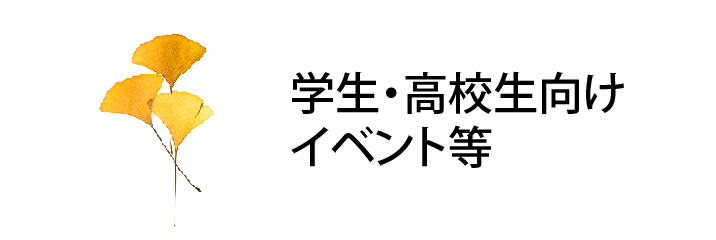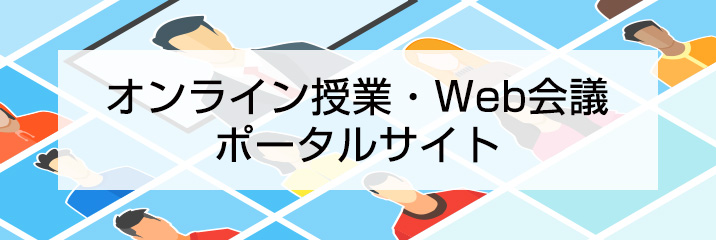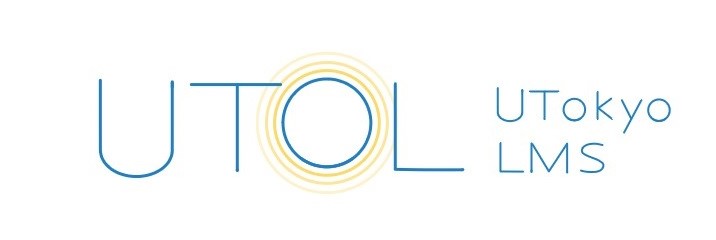0118007S 行政法演習(行政法の諸問題)宇賀教授
履修者へ
●10月1日連絡
人事院と公務員制度を取り上げます。
行政法概説Ⅲ(第4版)138~145頁(人事院)、322~363頁(公務員法総論)を予習しておいてください。
公務員法総論については、時間がない場合、322頁のPointのみで結構です。
●10月15日連絡
10月15日は、会計検査院と会計検査を取り上げます。
行政法概説Ⅲ(第4版)246~262頁を予習しておいてください。
会計検査院事務総長官房審議官(第3局・交通担当)の宮川氏にご出講いただきます。
●10月22日連絡
10月22日は、環境影響評価を取り上げます。
環境省大臣官房環境影響評価課課長の熊倉基之氏にご出講いただきます。
来週の授業では、六法を持っている方は、授業に持参してください。
●10月29日連絡
10月29日は、今大きな社会問題になっている所有者不明土地問題を取り上げます。
国土交通省大臣官房参事官(土地政策)の横山征成氏にご出講いただきます。
時間があれば、法学部図書館の雑誌室に所蔵されている『行政法研究』26号に
私が執筆した巻頭言を読んで(10分程度で読めると思います)、問題の所在を理解しておいてください。
●11月5日連絡
11月5日は、PFIを取り上げます。
概説Ⅲの509~513頁を読んで、PFIについての基礎的事項を理解しておいてください。
●11月8日連絡
11月8日は、月曜日の振替授業の日ですが、行政法の演習は、この日は行わず、来年の1月7日(月)5限に補講を行います。
●11月12日連絡
11月12日は、道路法を取り上げます。
概説Ⅲの506~509頁、513~521頁を読んで、公物法についての基礎的事項を理解しておいてください。
●11月19日連絡
11月12日の授業で道路法の原因者負担金と不法行為責任についての質問がありましたが、
宇賀克也「道路法上の原因者負担金制度の法律問題」成田頼明先生古稀記念『政策実現と行政法』
205頁以下で詳しく説明していますので、関心のある方は、それを参照してください。
11月19日は、行政委員会の代表例として公害等調整委員会を取り上げます。概説Ⅲの189~204頁
を読んで、行政委員会についての基礎的事項を理解しておいてください。
●11月26日連絡
11月26日は、法改正が検されている公益通報者保護法を取り上げます。
消費者委員会では、現在、同法の改正の検討が行われており、中間取りまとめが公表されています。
消費者委員会について、概説Ⅲ217頁のコラムを読んでおいてください。
●12月3日連絡
12月3日は、証拠に基づく政策立案(EBPM)について取り扱います。
EBPMとは、(1)政策目的を明確化させ、(2)その目的のため本当に効果が上がる行政手段は何かなど、「政策の基本的な枠組み」を証拠に基づいて明確にするための取組です。政策の改善に繋げるため、順次、三本の矢(行政事業レビュー、政策評価、経済・財政再生計画の点検・評価)の取組を通じ、EBPMを実践することとされており、政府にEBPM推進委員会が設置されています。
当日は、EBPM制度の立案に携わってきた白岩審議官にご出講いただきます。
政策評価について、概説Ⅲ84~85頁、168頁を読んでおいてください。
●12月10日連絡
12月10日は、人工公物としての性格を有する港湾についての公物管理法である港湾法について、国土交通省の菊地技監にご出講いただきます。
概説Ⅲ315~316頁(港務局)、541~543頁(公物管理における公私協働)、552~553頁(公物管理と公物運営)を読んでおいてください。
●12月17日連絡
12月17日は、今臨時国会で成立した水道法改正を中心に水道法について、改正法案の立案者の方にご出講いただきます。
水道法のコンセッション制度は、PFI法で導入されたコンセッション制度の特例としての性格を有しますので、概説Ⅲ511~513頁の公共施設等運営権の箇所を読んでおいてください。
●12月26日連絡
来週は振替授業が12月26日(水)5限に行われます。
個人情報保護委員会と個人情報保護法の問題を取り扱います。
個人情報保護委員会は、行政委員会の代表的なものですが、概説Ⅲ192~196頁の委員会の設置の根拠、職権行使の独立性の箇所、198~203頁の機能と権限、組織の箇所を読んでおいてください。
●1月7日連絡
1月7日は、自然公物の管理法の代表例として海岸法を取り扱います。
概説Ⅲ521頁6)から528頁6行目までの箇所を読んでおいてください。